開発コストの削減が期待できる「オフショア開発」は、多くのプロジェクトにおいて検討される選択肢の1つです。しかし、「言葉や文化の違いで、上手くコミュニケーションが取れないのでは?」など、海外企業に依頼する特性上のリスクに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、オフショア開発のよくある失敗事例をもとに、その原因と対策を詳しく解説します。さらに、本当にオフショア開発を選ぶべきかどうか、比較対象となる選択肢も合わせて紹介します。自社に合った開発手法を見つける際の参考にしてみてください。
【目次】
オフショア開発のよくある失敗事例と原因
オフショア開発はコスト削減を期待できる一方、言語や文化の違いからプロジェクトが想定通りに進まないケースも少なくありません。ここでは、代表的な3つの失敗事例を紹介します。あらかじめ失敗のパターンを把握し、対策を講じておきましょう。
設計書と異なる成果物が納品された
オフショア開発でとくに多い失敗のひとつが、設計書と異なる成果物が納品されてしまうケースです。
失敗の要因としてまず挙げられるのは、日本側と現地開発チームの橋渡し役である「ブリッジSE」との連携不足です。日本側が伝えた細かな仕様が翻訳の過程で抜け落ちたり、ニュアンスが変わって伝わってしまったりするケースは少なくありません。
また、海外では日本に比べて人材の流動性が高く、プロジェクト途中で担当者が交代することも頻繁に起こります。その際、引き継ぎが不十分だと、仕様やプロジェクト経緯の理解度にズレが生じ、成果物の品質低下に直結します。
納品後に予期せぬ不具合や修正が発生した
オフショア開発では、納品後に想定外の不具合が発覚し、手戻りや追加修正が発生するケースも目立ちます。
よくある原因のひとつが、日本側と現地側の開発環境の違いです。現地のテスト環境では問題なく動作していても、OSやデータベース、ライブラリのバージョンが日本国内の本番環境とわずかでも異なれば、深刻なエラーを引き起こす可能性があります。
また、ソースコードのコメントが不十分だったり、現地の言語で書かれていたりすることで、納品後の保守・運用フェーズで問題になることもあります。日本語が堪能なブリッジSEでも、ドキュメント作成やコーディング規約の徹底まで管理が行き届かない場合、コードが属人化し、改修時に新たなバグを生みかねません。
納期の遅延が発生した
コスト削減を期待してオフショア開発を選んだにも関わらず、納期の遅延によってかえってコストがかさんでしまう可能性もあります。
まず原因として考えられるのは、単純な時差の認識ミスです。たとえば、開発先がベトナム(時差-2時間)の場合、「日本時間の18時」をデッドラインと明確に伝えなければ、現地時間で作業され、納品が遅れる可能性があります。また、現地の祝日を把握しておらず、作業がストップしてしまうケースも起こり得ます。
失敗事例から学ぶ、オフショア開発の成否を分けるポイント
では、なぜオフショア開発は成功するプロジェクトと失敗に終わるプロジェクトに分かれてしまうのでしょうか。前述の失敗事例を分析すると、成功と失敗を分けるポイントを以下の3つに整理することができます。
- コストと品質のバランス感覚
- プロジェクトへの主体的な関与
- 異文化への理解とリスペクト
コストと品質のバランス感覚
オフショア開発はコストを削減できる点が大きなメリットですが、目先の安さだけでパートナーを選定すると、結果的に品質不足による手戻りや、管理コストの増大を招きかねません。
価格には、品質や開発体制が反映されます。技術力、管理体制、そしてリスク要因まで含めた「トータルコスト」を見極め、自社の求める品質に見合うパートナーを冷静に選択する。そのバランス感覚が、成否を分けるポイントです。
プロジェクトへの主体的な関与
オフショア開発は、単なる作業の委託ではなく、国を越えた協業プロジェクトです。
そのため、「仕様書を渡して終わり」ではなく、主体的にプロジェクトを管理し、進捗や課題をこまめに共有する体制を築くことが重要です。発注者側が積極的に関与し、パートナーと一体となってプロジェクトを推進する姿勢が、円滑なコミュニケーションと高い品質を生み出します。
異文化への理解とリスペクト
オフショア開発には、言語の壁はもちろん、仕事の進め方や価値観といったビジネス文化の違いを理解し、尊重する姿勢が欠かせません。
日本では「暗黙の了解」で進むことも、海外では「契約書や仕様書がすべて」というのがスタンダードです。曖昧さを排除し、明確なドキュメントでコミュニケーションをとる必要があります。
日本のやり方を一方的に押し付けるのではなく、相手の文化をリスペクトし、お互いの長所を活かせるような協力体制を築こうと努力すること。それが、信頼関係の基盤となり、プロジェクトの成功確率を大きく高めるでしょう。
オフショア開発の失敗を防ぐ6つの対策
ここからは、オフショア開発の失敗を防ぐ具体的な対策を紹介します。
- パートナーの実績を確認する
- コミュニケーションの仕組みを構築する
- プロジェクトメンバーの固定を交渉する
- 相手の文化を尊重し、計画に反映させる
- まずはスモールスタートで始める
- 適正価格で依頼する
①パートナーの実績を確認する
まずは、依頼を検討している会社の実績を確認しましょう。とくに自社が依頼したいプロジェクトが明確な場合は、類似するシステムやサービスの開発実績が豊富な会社を優先すべきです。
また、開発実績については、概要だけでなく担当範囲や体制の詳細も確認しておきましょう。設計などの上流工程から携わった経験が豊富か否かは、開発会社の総合的な技術力や提案力を見極める重要な指標となります。ミスマッチを防ぐためにも、表面的な実績だけで判断しないことが重要です。
②コミュニケーションの仕組みを構築する
物理的な距離があるオフショア開発では、「いつでも話せる」という意識ではなく、以下のようにコミュニケーションの機会を仕組み化することが重要です。
- 定例会議の設定:
週に1回など、ブリッジSEと必ず進捗や課題を同期する場を設ける。 - 課題管理ツールの導入:
Q&Aや課題をリアルタイムで共有できるシートやツールを用意し、疑問や問題が放置されることを防ぐ。
こうした仕組みづくりが、認識のズレを早期に発見し、手戻りのリスクを最小限に抑えます。
③プロジェクトメンバーの固定を交渉する
海外では人材の流動性が高く、プロジェクトの途中でメンバーが交代することは珍しくありません。しかし、十分な引き継ぎが行われないまま担当者が変わってしまうと、成果物の品質が低下するリスクがあります。そのため、契約段階で「主要メンバーを固定すること」を交渉してみましょう。
メンバーの固定が難しい場合は、「引き継ぎ期間を最低2週間設ける」「ドキュメント化を徹底する」といった代替案を提示し、ノウハウが円滑に継承されるルールを定義しておくことが有効です。
④相手の文化を尊重し、計画に反映させる
オフショア開発を進めるうえで、現地のビジネス文化や習慣の違いを理解しておくことは不可欠です。
たとえば、ベトナムのテト(旧正月)のように、長期休暇の時期は日本とは異なります。こうした年間行事や祝日のタイミングをあらかじめ把握し、開発会社が稼働できない日をスケジュールに反映しておきましょう。
加えて、仕事に対する価値観やコミュニケーションスタイルの違いにも注意が必要です。
日本ではニュアンスで伝わる表現でも、海外の担当者には意図が正確に伝わらないことがあります。
曖昧な指示は誤解を招き、作業の手戻りにつながる可能性もあるため、具体的で明確な指示を心がけることが大切です。口頭やチャットだけで済ませず、ドキュメント化による正確な情報共有を徹底しましょう。
⑤まずはスモールスタートで始める
初めてのオフショア開発で、いきなり大規模なプロジェクトを丸ごと委託するのはリスクが高い選択です。まずはリスクの低い領域から「スモールスタート」することを推奨します。
特に、システムの根幹を決める要件定義や基本設計といった上流工程は、コミュニケーションの齟齬が致命傷になりやすいため、自社(国内)で固めるのが安全です。
例えば、仕様がFIXした後の製造・テスト工程に絞って依頼することで、役割分担が明確になり、オフショア開発のメリットを享受しやすくなります。まずは小さな成功体験を積み重ね、徐々に信頼関係を築いていきましょう。
⑥適正価格で依頼する
コスト削減は重要ですが、極端に安い見積もりには必ず理由があります。その安さが、エンジニアの経験不足や実績の乏しさから来るものでないか、根拠をしっかりと確認しましょう。
海外では、契約外の作業には厳格に追加費用が発生するのが一般的です。目先の安さで契約した結果、追加費用が重なり、かえって高くつくケースも少なくありません。
開発パートナーに最大限のパフォーマンスを発揮してもらうためにも、成果に見合う適正価格で依頼するという発注側の意識が、最終的にプロジェクトの品質を高めるでしょう。
オフショア開発のデメリットを補う、国内での開発手法
オフショア開発には管理コストやコミュニケーションの壁といった特有の難しさがあります。これらのデメリットを回避しつつ、開発を推進するための選択肢として「ニアショア開発」と「ラボ型開発※」をご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクトに最適な手法を見つけましょう。
※ラボ型開発は契約形態の一種であり、オフショア・ニアショアの双方に採用される場合もあります。
ニアショア開発
ニアショア開発は、首都圏の企業が、開発業務を国内の地方都市にある企業へ委託する手法です。たとえば、東京の企業が札幌や福岡の開発会社に依頼するケースが挙げられます。
最大のメリットは、言語・文化・時差の壁がなく、コミュニケーションが非常に円滑な点です。国内の商習慣を前提にやり取りできるため、仕様の誤解や認識のズレといったリスクを大幅に軽減できます。
オフショア開発ほどのコスト削減効果は見込めませんが、成果物の品質を重視し、円滑なプロジェクト進行を求める場合に適した選択肢です。
ラボ型開発
ラボ型開発とは、一定期間、自社専用の開発チームを準委任契約で確保する形態です。成果物に対してではなく、エンジニアの労働時間に対して費用を支払います。
最大のメリットは、柔軟性の高さです。仕様変更や優先順位の見直しに素早く対応できるため、アジャイル開発との相性が抜群です。また、同じメンバーが継続して開発にあたるため、自社のビジネスやシステムに関する知識・ノウハウがチーム内に蓄積され、開発スピードと品質の向上も期待できます。
自社に開発の主導権を残しつつ、パートナーとして信頼できる専属チームを構築したい企業に最適な手法です。
ラボ契約の詳細をチェック!
| 比較軸 | オフショア開発 | ニアショア開発 (主に請負契約) | ラボ型開発 (準委任契約) |
|---|---|---|---|
| コスト | ◎ | △ | △ |
| コミュニケーション | △ | ◎ | ◎ |
| 品質の安定性 | △ | 〇 | ◎ |
| 体制の柔軟性 | × | △ | 〇 |
| ノウハウの蓄積 | × | △ | ◎ |
| プロジェクトの主導権 | × | △ | ◎ |
開発体制にお悩みの方はラクスパートナーズにご相談ください
オフショア開発を活用すれば、低コストでシステム開発を依頼できます。しかし、そのメリットを最大限に享受するには、言語や文化の壁を乗り越えるためのプロジェクトマネジメント力が不可欠であることも事実です。
そのため、「コストは抑えたいが、品質が落ちるのは避けたい」「海外とのやり取りは、自社だけで管理しきれそうにない」とお悩みの場合は、国内での開発手法も有効な選択肢といえるでしょう。
ラクスパートナーズのITエンジニア派遣サービスは、いわば「国内で実現するラボ型開発」です。貴社がプロジェクトの主導権を握ったまま、必要なスキルを持つ正社員エンジニアで専属チームを柔軟に構築できます。
充実した研修をクリアした高い技術力を持つエンジニアが、貴社のチームの一員としてプロジェクトの成功をサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。



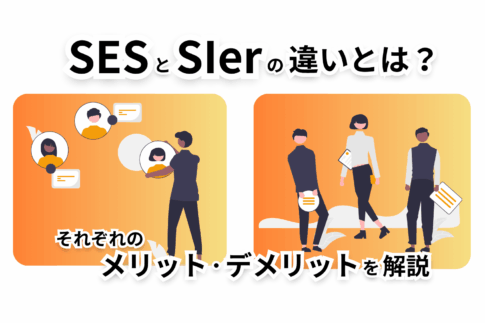


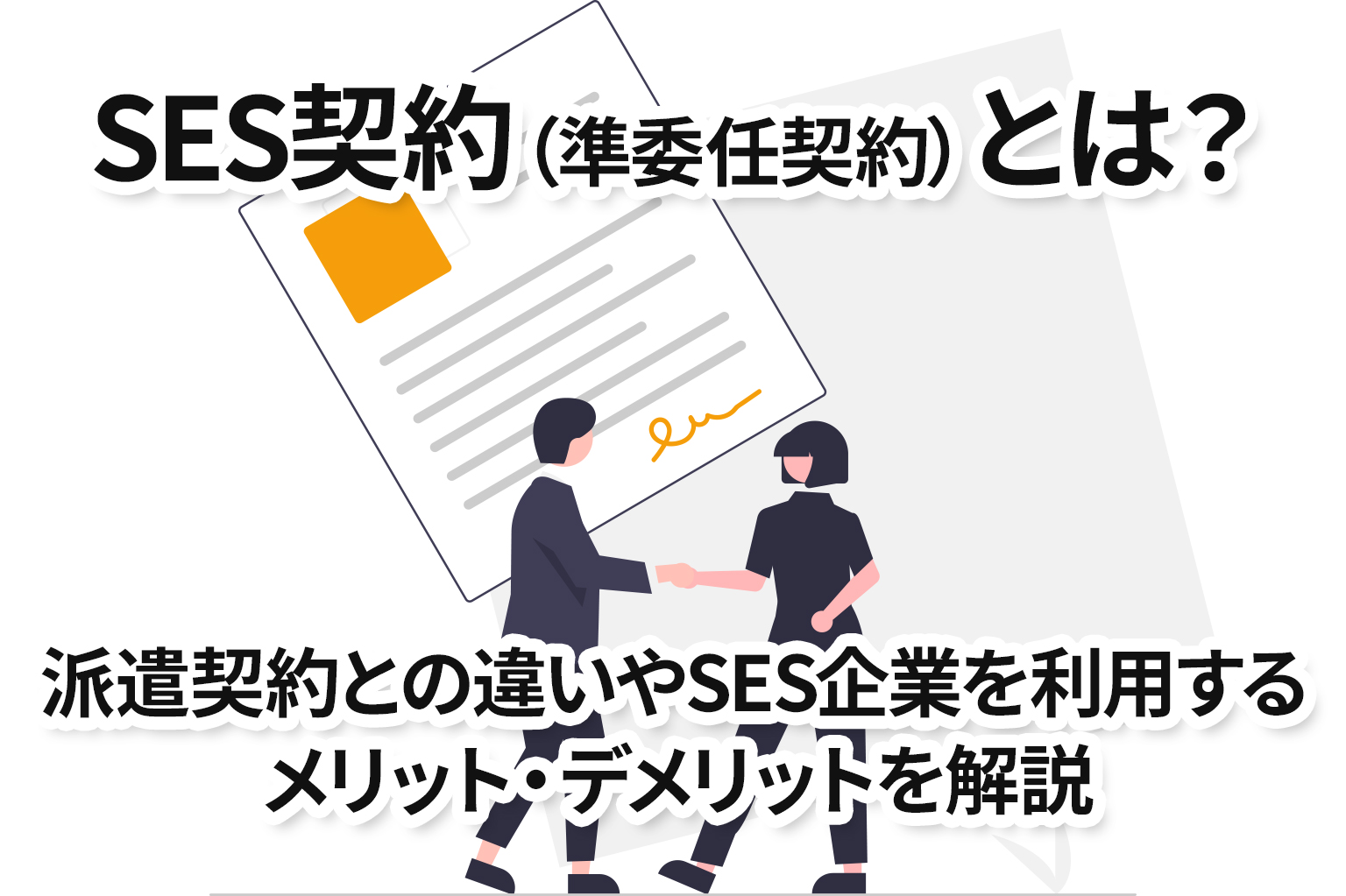


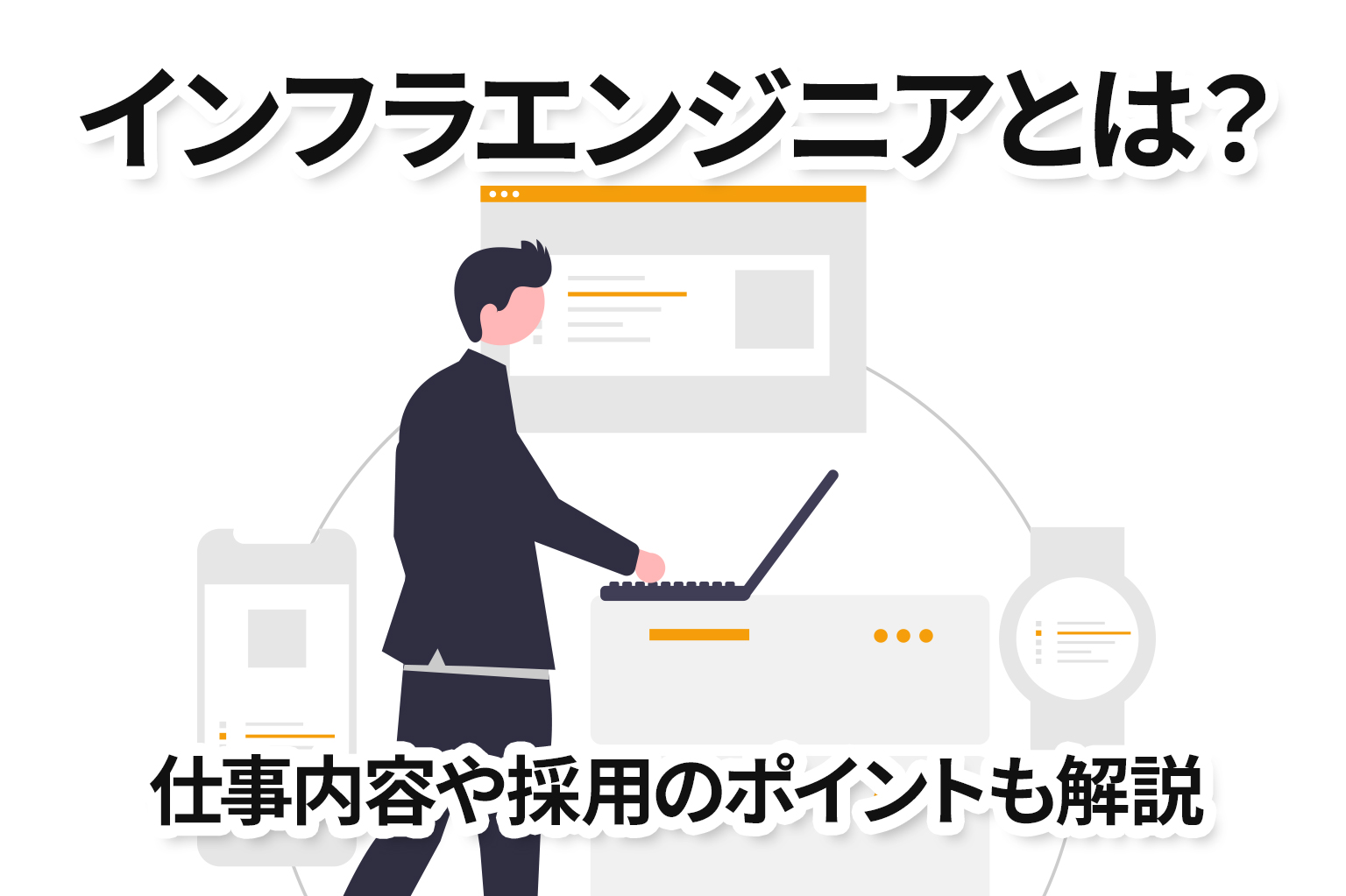
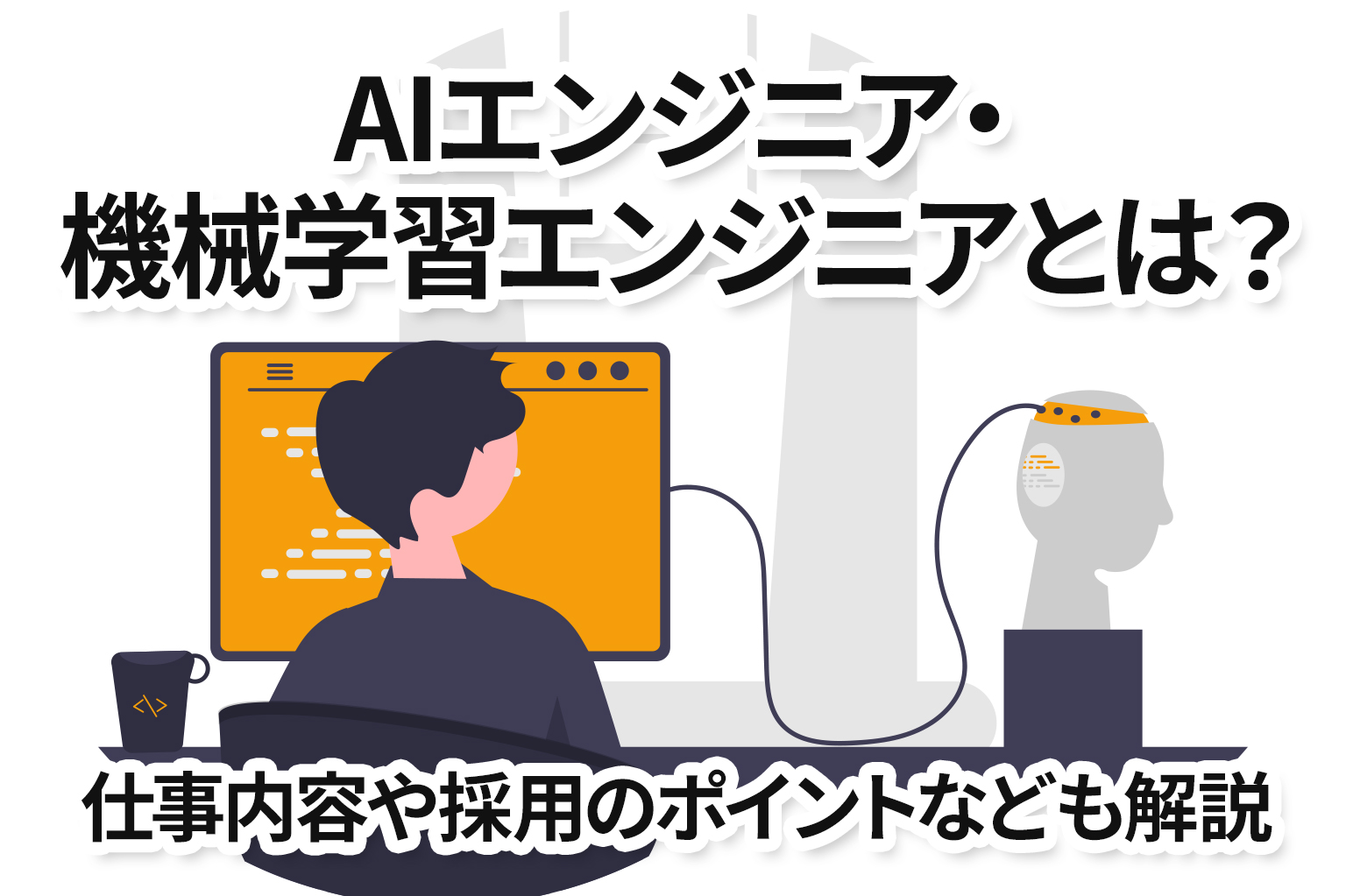

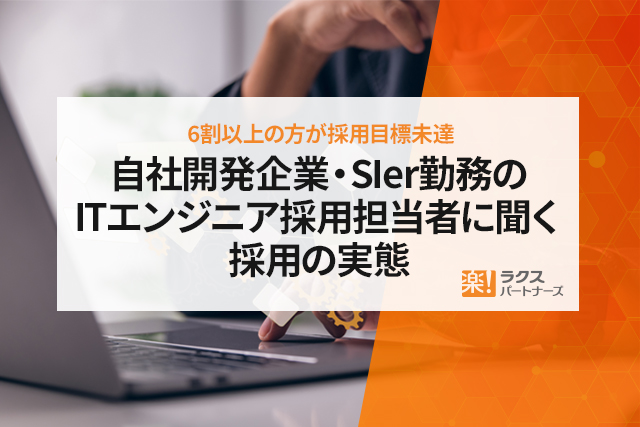
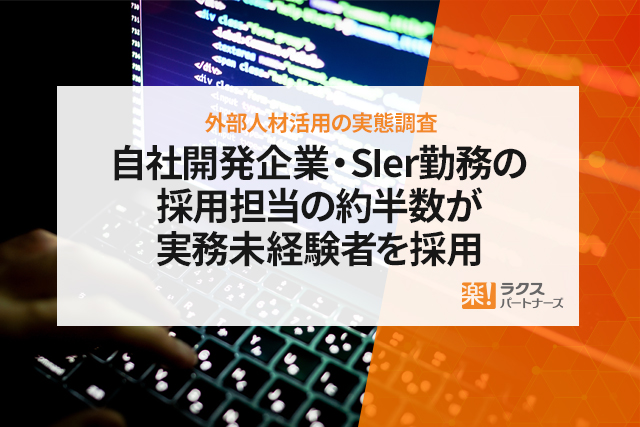
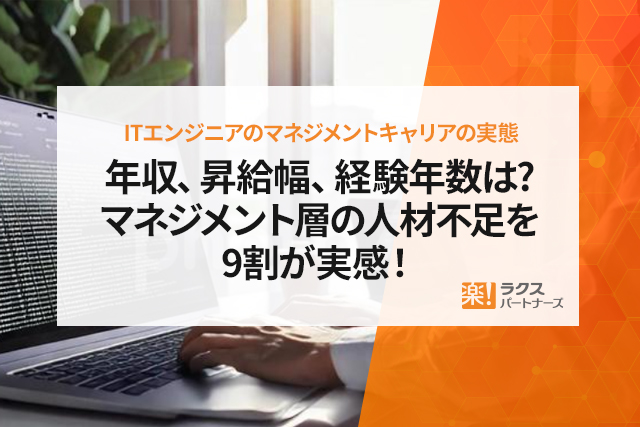
\優秀なITエンジニアが楽々みつかる/
ITエンジニア派遣ならラクスパートナーズ
ITエンジニア不足のよくあるお悩み
私たちの生み出したITエンジニアが御社のIT課題を解決!
ラクスパートナーズは、自社で採用・育成したITエンジニア社員を常駐派遣。
Web開発、QA、インフラ、機械学習、データサイエンティストなど、
それぞれに特化した人材がいるから、どんなご要望にも即戦力で活躍する
ITエンジニアをご提案できます。DX推進にも貢献します!
資料請求
【最短1分!】お問い合わせ