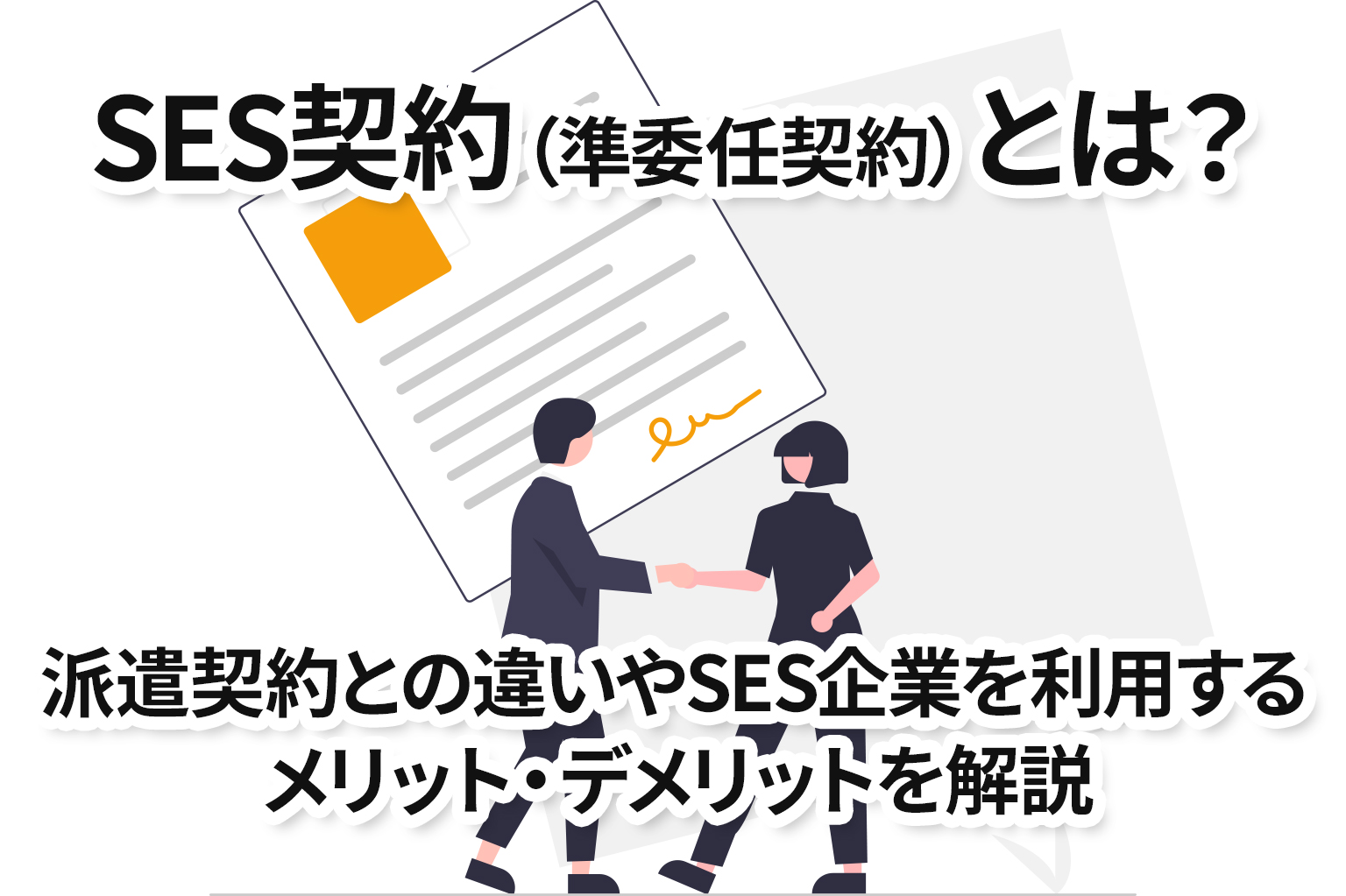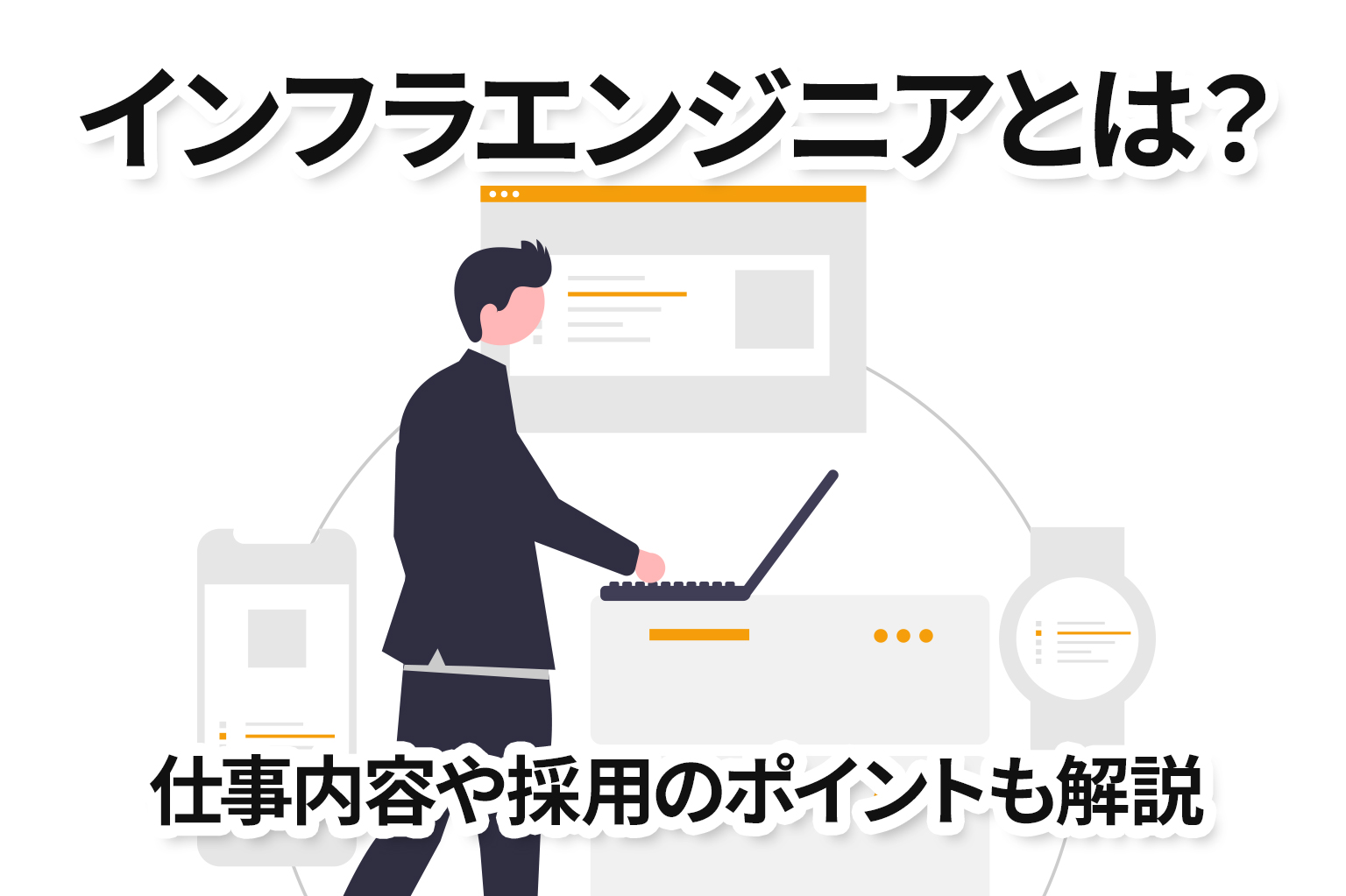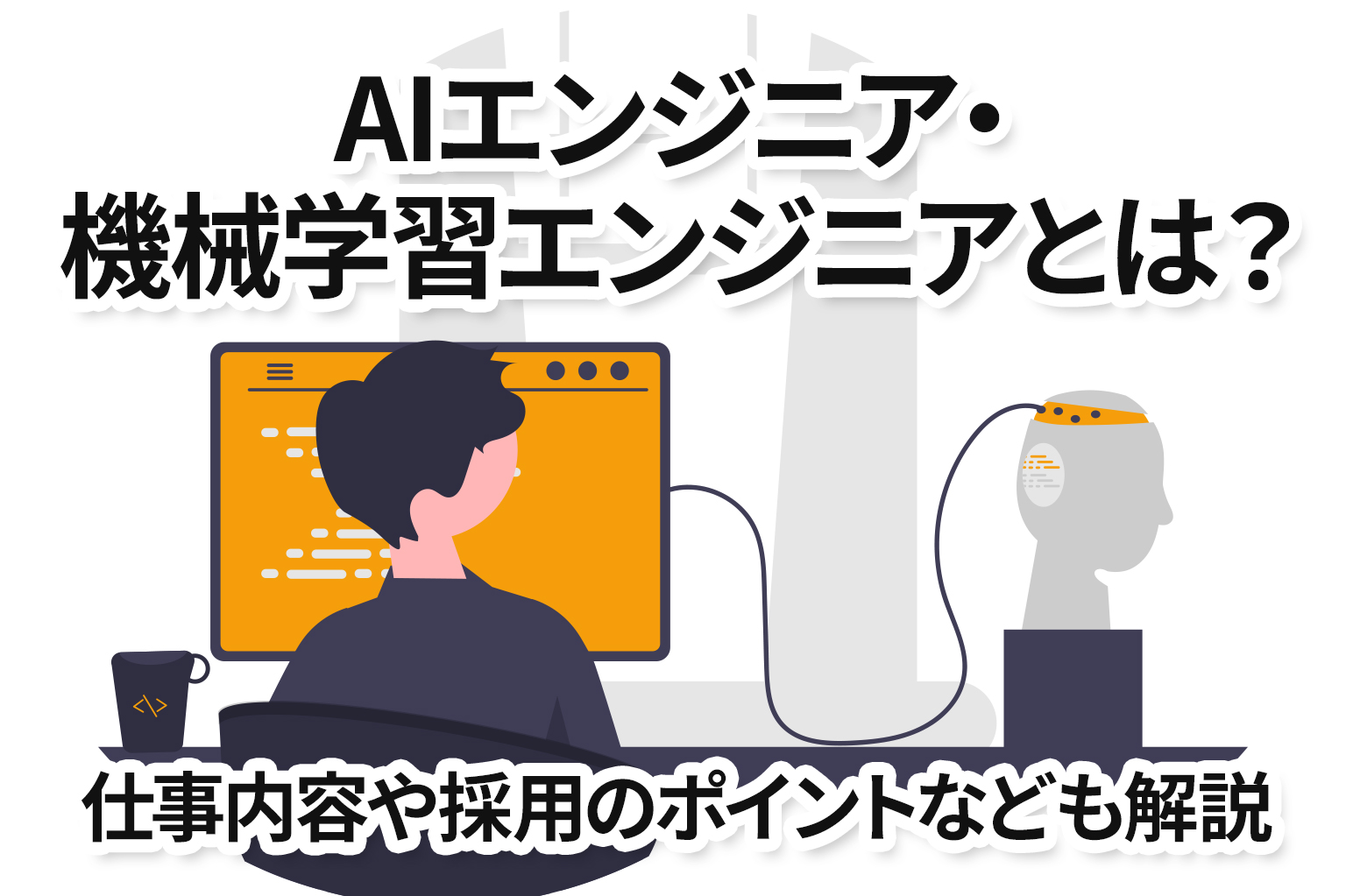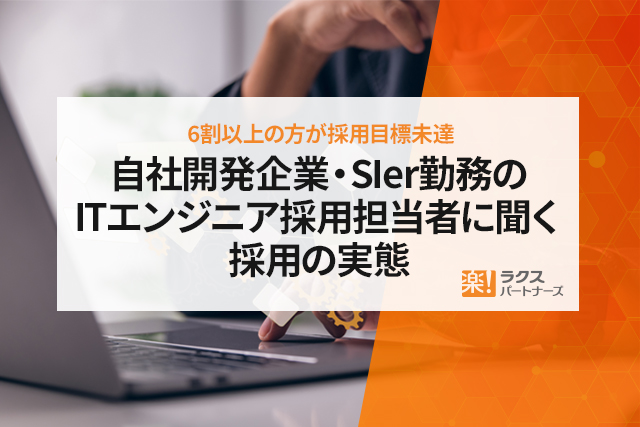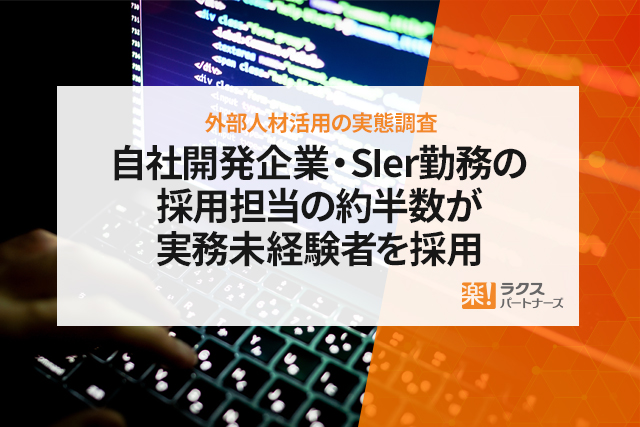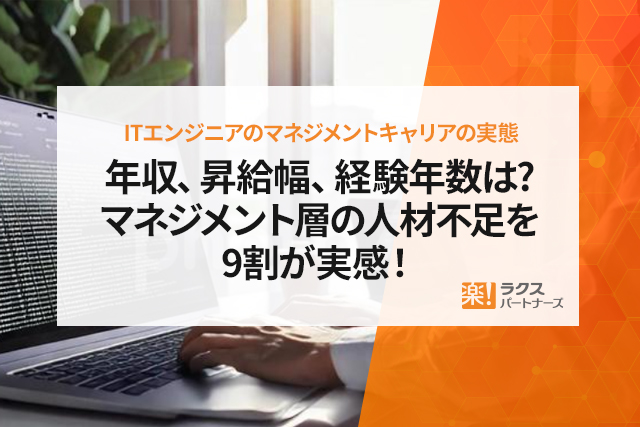DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性があらゆる企業で高まっている中で、
「開発スピードが遅い」「変化に即応できない」「ベンダーに依存している」など、
開発体制にまつわる課題が顕在化しています。その要因の一つとして挙げられるのが、外注中心の開発体制です。
急速に変化する市場に対応しながら「DX」を実現するためには、スピーディで柔軟な開発体制が不可欠です。その解決策として今多くの企業が注目しているのが、「DXの内製化」です。
本記事では、非エンジニアの人事担当者にもわかりやすく、DXと内製化の関係性、人材戦略のポイント、内製化を支える文化や制度、そして成功事例までを詳しく解説します。
【目次】
DXとは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術やデータを活用して、業務プロセスやビジネスモデルを継続的に変革していく取り組みです。単に紙業務を電子化したり、業務システムを導入したりすることだけがDXではなく、企業の組織や文化そのものを変えていく動きが含まれます。
近年では、顧客ニーズや市場環境の変化が加速しており、それに対応するには、スピーディかつ柔軟に意思決定し、施策を実行できる体制が不可欠です。こうした環境下では、一度きりの改善ではなく、アジャイル開発のような「仮説を立てて試す→結果を見て即座に改善する」といった短いサイクルでの継続的な変革が求められます。
DXの実現には、テクノロジーだけでなく、それを支える組織や体制、プロセスの見直しも不可欠です。システム導入だけで終わらない、企業全体での変革の推進が求められています。
内製化とは?
外注に頼らず、自社で開発を担う体制
内製化とは、業務システムやアプリケーションの開発・運用を、外部のベンダーに委託せずに自社内で担う体制を構築することを指します。たとえば、これまで開発や改修を外部企業に発注していた業務について、自社のチームが主導して対応できるようになる状態です。
DXが求められる今、システムやサービスの改善をすばやく繰り返していくには、現場が自ら手を動かせる体制が不可欠です。こうした背景から、外部依存から脱却し、社内で自律的に開発・運用できる「内製化」の動きが注目されています。
外注体制の課題
外注は、専門性のある開発リソースを短期間で確保できるという点で有効ですが、中長期的にはいくつかの課題が存在します。
ノウハウが社内に残らない
外注では、プロジェクトの実行そのものを外部に依頼するため、社内メンバーが開発や設計の本質的な部分に触れる機会が限られてしまいます。要件定義やレビューに関わるとしても、課題の背景や設計思想などは共有されないまま進むケースも多く、社員自身が知識や経験を得るチャンスが失われがちです。この状態が続くと、次のような弊害が想定されます。
- 社員がプロダクトの改善提案を出せない
- 問題発生時に自力で原因特定・対処ができない
結果として、「いつまで経っても自社にITの知見が蓄積されない」という悪循環に陥る恐れがあります。
スピード感の不足
外注体制では、開発や修正を依頼するたびに「要件のすり合わせ」「契約・見積もり調整」「スケジュール調整」など、さまざまなプロセスが必要になります。一見すると効率的に見える外注も、次第に以下のようなタイムラグを生み出すケースもあります。
- 要望が現場から上がっても、反映までに数週間かかる
- 社内の判断スピードと外部の開発速度にギャップが出る
特にDXのように「仮説検証→改善→再実装」を短期間で何度も回すことが求められる領域では、このスピード感の欠如が、競争力低下の要因となり得るでしょう。
セキュリティ面での不安
外注体制では、どこで誰がデータに触れているのか、社内からは見えにくくなることがあります。特に、個人情報や業務データなどを扱うDXプロジェクトでは、情報漏洩や不正アクセスといったリスクへの備えが不十分だと、大きな問題につながりかねません。
- セキュリティ体制がベンダー任せで、自社では管理できていない
- セキュリティリスクが発生した際、初動対応が遅れる
とくにDX推進では、個人情報や業務データといったセンシティブな情報を扱う機会が増えるため、情報統制の弱さが企業リスクに直結します。
DX内製化のメリット
こうした外注の限界を打破するために、今あらためて内製化の価値が注目されています。こでは、主なメリットを3つ紹介します。
ノウハウの蓄積
内製化によって開発等の知見が組織内に蓄積されれば、課題に対して再現性ある対応や、ナレッジの横展開が可能になります。これは単なる「引き継ぎの効率化」ではなく、組織としての学習能力を高め、持続的な改善文化を築くという点で、非常に大きなメリットです。
スピードと柔軟性の確保
市場ニーズの変化や顧客の要望にスピーディに対応するには、開発サイクルの短縮とタイムリーな機能改修が不可欠です。社内にエンジニアや開発体制を整えることで、「仮説検証→改善→再リリース」といったPDCAサイクルを自社主導で回すことができるようになります。これが、競合優位性を維持する鍵となります。
セキュリティリスクの低減
個人情報や機密情報を扱う開発業務において、外部委託による情報漏洩リスクは無視できません。内製化はデータの取り扱いを社内で完結できるため、セキュリティガバナンスを強化できる点も重要です。
特にDXでは、スピーディな仮説検証と継続的な改善が求められるため、状況変化に即応できる内製体制は、変革を支える実行基盤として不可欠なものとなっています。
ITエンジニアをお探しですか?
Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで
採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。
まずはご相談ください!
DX内製化の課題
内製化は企業の自走力・競争力を高める有効な手段である一方で、導入にあたってはさまざまなハードルが存在します。メリットばかりが注目されがちですが、現場レベルの負担や体制構築の難しさを無視した内製化は、かえって非効率や混乱を招く恐れもあります。
ここでは、DX内製化推進時によく挙げられる3つの代表的な課題を紹介します。
初期投資とランニングコスト
内製化には、初期段階で一定の投資が不可欠です。
エンジニアの採用や研修費、必要なハードウェアやソフトウェアの導入、社内における業務フローの整備など、初期段階で多くのコストと工数を要します。また、開発を一度始めたら終わりではなく、保守・改修・セキュリティ対応など、継続的にランニングコストも発生します。
これにより「外注のほうが楽」「コストが読みにくい」といった声が社内で出やすくなり、意思決定の障壁になることも少なくありません。
ただし中長期的に見ると、外注による毎年の契約費やベンダー対応コストよりも、内製化によってノウハウを蓄積し、同じ開発を再利用・横展開できることのほうが、結果的に費用対効果が高くなるケースも多く存在します。
DX人材の確保が困難
「できることならDXを内製で進めたい」と考える企業は多くても、実際にDX推進を担える人材が圧倒的に不足しているというのが現状です。
高度なスキルを持つエンジニアやデジタル人材は市場でも引く手あまたで、転職競争が激化しています。加えて、即戦力だけを求めた採用では社内文化に合わなかったり、短期離職のリスクも高まります。
また、採用できたとしても社内に十分な受け入れ体制(オンボーディング・育成環境・明確なキャリアパス)がないと、スキルが活かされないままに終わってしまうことも少なくありません。
属人化のリスク
内製化を急ぐあまり、一部の優秀な人材に開発や運用を任せきりにしてしまうことで、逆に業務がブラックボックス化してしまうケースも見られます。
これは「内製化のつもりが、実質的には“個人依存”になってしまっている」状態です。万が一、そのキーパーソンが離職した場合、プロジェクトが停止してしまうというリスクにもつながります。
また、ナレッジの共有や業務標準化がなされていないと、新たなメンバーの育成や引き継ぎがうまくいかず、チームとしての拡張性や再現性を失う要因になります。
▼DX化についてはこちらの記事もチェック!
DX内製化で人事が押さえておきたい3つのポイント
DXと内製化を同時に推進するには、「人材」「文化」「制度」の3つをバランスよく整えることが不可欠です。そしてそれらを統合し、継続的に機能させていく役割を担うのが、企業の人事部門です。
採用の見直し
DXや内製化を進めるには、従来の採用基準や要件を一度見直す必要があります。技術力だけでなく、組織の中でどう動けるか、どんな行動特性を持っているかという点が、より重要になってきているためです。
- 採用要件を行動特性で定義する
スキルマッチだけでなく、「課題を自ら発見できる」「チームと協調して動ける」「学び続けられる」といった行動面の資質を重視した要件定義を行いましょう。社内で活躍しているDX人材の共通点を分析し、言語化しておくことがポイントです。
- 採用チャネルと打ち出し方の工夫
技術イベントへの登壇、テックブログの運用、社員インタビューの発信などを通じて「内製化に本気で取り組んでいる会社」というブランディングを強化することが、優秀な候補者との接点づくりにつながります。
文化と評価制度の整備
どれほど優秀な人材を採用しても、挑戦や改善を許容しない文化では力を発揮できません。人が動き、学び、成長していくためには、それを後押しする組織の文化と仕組みが欠かせません。
- 挑戦と学習を評価する制度づくり
成果だけでなく、プロセスに着目した評価制度を設計することで、トライ&エラーをポジティブに受け止める文化が育ちます。ナレッジ共有やコードレビュー、改善提案などの活動も適切に評価対象とするべきです。
- 組織横断の連携を促進
DXは1部門だけで完結するものではありません。営業・企画・人事などが連携するためには、人事部門がハブとなり、部門間の共通目標やチーム設計を支援していく必要があります。
育成とチーム設計
採用した人材を活かし、長期的に育てていく体制がなければ、内製化は根づきません。属人化せずに成長を促す仕組みと、外部人材を含むチーム運用設計がカギを握ります。
- キャリアと育成計画の設計
キャリアパスやスキルアップの道筋を明確にすることで、社員の成長意欲と定着率が高まります。また、職種ごとに必要なスキルと育成フェーズを定義し、OJT・メンター制度・eラーニングなどを組み合わせた継続的な学習環境を整えましょう。 - ハイブリッド体制を見据えた人材運用
自社内だけで完結しきれない部分については、ビジネスパートナーや外部エンジニアと協業するハイブリッド体制を構築しましょう。その際も評価制度やナレッジ共有の仕組みを整えることで、チーム全体が成長できる設計にすることが重要です。
▼正社員型派遣についてはこちらの記事もチェック!
【参画事例】ラクスパートナーズの内製化支援
ここでは、当社ラクスパートナーズが内製化を進めている企業様へ参画した事例をご紹介します。
株式会社SUPER STUDIO様
D2Cビジネスを支援するECプラットフォーム「ecforce」の提供をはじめ、コマース領域でソリューション開発・運用を行うテクノロジーカンパニーで、自社プロダクトの開発力と現場支援のノウハウを活かし、クライアント企業の成長支援にも注力されています。
課題・背景
- インフラ運用業務が属人化しており、担当者不在時の対応に課題があった
- 運用業務の手順がドキュメント化されておらず、再現性に乏しい開発環境
- 外部依存から脱却し、内製化を見据えた自律的な運用体制を構築したいと考えていた
効果
- 主体性の高いエンジニアをアサインし、運用業務の棚卸しから標準化・手順書化までを支援
- 経験の浅いメンバーでも短期間でキャッチアップ可能な体制が構築され、属人化が解消
- 正社員とパートナーがフラットに協働するチームが機能し、将来的な内製化に向けた足場が整備された
まとめ
内製化は、単なる開発手法の見直しではなく、企業の競争力を左右する戦略的な選択です。そして、その成否は「人材」にかかっています。
人事部門には、
- DX人材の採用と育成
- 組織文化の変革
- 内製化を支える制度設計 など、これまで以上に経営に近い視点が求められています。
自社の未来を切り拓くDXの基盤として、開発体制とそれを担う人材の強化に、人事が積極的に関与していくことが、今まさに必要とされているのです。
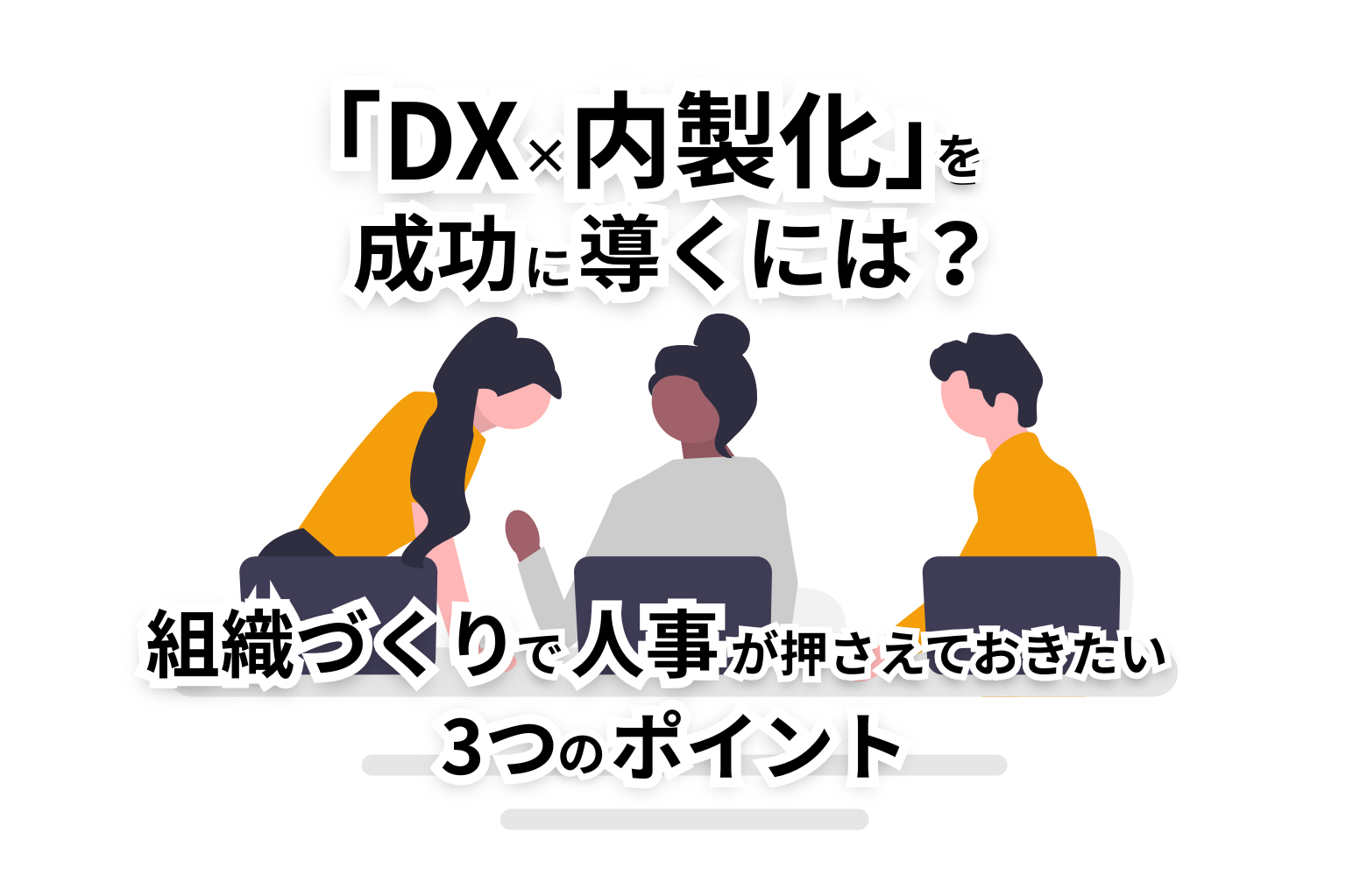





の役割とは?PM・PLとの違いと採用のポイントを解説-485x323.png)