派遣社員の受け入れを行っている企業にとって、「抵触日」は見過ごせない重要なキーワードです。これは、労働者派遣法により、同一の部署や同一の派遣社員を3年を超えて継続して受け入れることが原則できないという、いわゆる「3年ルール」によって発生する期限のことを指します。
しかしながら、派遣制度にあまり馴染みがない採用担当者にとっては、
「どの部分がどのように抵触するのか」というように対応に戸惑うケースも少なくありません。
本記事では、「抵触日」の基本的な考え方から、個人単位・事業所単位の違い、実際に抵触日を迎えた際の具体的な対応策まで、制度に詳しくない方にもわかりやすく解説します。後半では、抵触日を回避できる「正社員型派遣」の活用方法についてもご紹介します。
【目次】
抵触日とは?
派遣契約における抵触日とは、「派遣契約期間が満了した翌日」を指します。
これは、2015年9月30日に施行された「労働者派遣法」にて、企業側が無期限に派遣社員を受け入れ続けることを防ぐために定められた制度です。
また、派遣の期間制限には2つの種類があります。
- 事業所単位の期間制限
- 個人単位の期間制限
どちらも原則3年のため、「3年ルール」とも呼ばれていますが、カウントの仕方や影響範囲が異なるため、混同しないようにすることが大切です。
抵触日には「事業所単位」と「個人単位」がある

出展:厚生労働省「派遣の皆様へ」
事業所単位の抵触日とは
事業所単位の抵触日とは、同一の課や部署など、一定の事業所単位*における受け入れ期間に関する制限であり、原則として、同一の事業所・組織で派遣労働者を受け入れられる期間は3年までとされています。なお、ここでいう3年は、最初に派遣を受け入れた日も含めてカウントされます。
例えば、ある部署で派遣社員Aを「2025年4月1日」から受け入れ始めた場合、事業所単位としては「2028年3月31日」が上限となります。たとえその間に派遣社員B、Cと人を入れ替えたとしても、事業所としてのカウントは継続されるため、事業所単位での満期が適応されるという判断になります。
また、事業所単位での抵触日に関しては、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見聴取手続をした場合のみ、3年を限度として派遣可能期間を延長することが可能です。
しかし、この場合は別の派遣労働者の場合のみ、同一の課に派遣可能なため、同一の派遣社員が同一の課にて3年以上働くことは、結果として不可能になります。
* 事業所単位の期間制限における「事業所」とは、以下の3点を満たしたものを指します。
個人単位の抵触日とは
個人単位においても、同一の派遣社員が同一の組織単位*で勤務できる期間は原則3年までと定められています。
ここでいう「同一の組織単位*」とは会社全体ではなく、一般的には課や部署などを指します。たとえば、営業部で3年働いた派遣社員は、同じ営業部ではそれ以上勤務できません。
なお、個人単位の期間制限には延長の仕組みは存在しません。
よく混同されがちな「意見聴取手続き」は、事業所単位の抵触日に対して適用される延長措置であり、個人単位には適用されないため注意が必要です。
ただし、業務内容が大きく異なる部署(例:開発部から営業部など)に異動し、新たな契約として就業する場合(=別の組織単位での就業)は、同一人物でも勤務が可能になる場合があります。
* 組織単位とは、厚生労働省「平成27年労働者派遣法改正の概要」にて以下のように定義されています。
抵触日を迎えたときの対応策
もし、派遣社員の3年の抵触日を迎えてしまった場合、契約をそのまま更新することは原則できません。しかし、一定の条件や工夫によって、継続的な人材活用や代替手段を講じることは可能です。具体的には以下の4つの方法を検討されます。
以下にて詳しく解説していきます。
部署・課を変更する
抵触日の対象となるのは「同一の組織単位」での勤務です。そのため、派遣社員の業務内容や配属先を変更し、別組織として再契約することで、新たに開始できる場合があります。
(前提として、前述した組織単位の定義上、別組織と判断されることが必要です。)
派遣社員の交代
抵触日を迎える派遣社員との契約を終了し、別の人材に交代することで、部署内での受け入れを継続することも可能です。ただし、引き継ぎや業務の属人化リスクには注意が必要です。
直接雇用に切り替える
3年の期間制限を迎えたタイミングで、派遣社員を正社員や契約社員として自社採用することで、継続的な戦力として活用できます。
本人が既に業務に精通している場合、教育コストも少なく即戦力として貢献しやすい選択肢です。
派遣元での無期雇用型派遣の検討
今後も同じ業務で長期的に派遣社員を受け入れたい場合は、最初から「抵触日が発生しない」無期雇用派遣(正社員型派遣)を選ぶという方法があります。
この場合、派遣元で正社員として雇用されているため、3年の期間制限にかからず、長期的な就業が可能です。
ITエンジニアをお探しですか?
Web開発、インフラ、AI・機械学習、QA領域まで
採用率4%の厳選された正社員エンジニアのみをご提案。
まずはご相談ください!
派遣制限を受けないパターンとは?
ただし、すべての派遣に期間制限があるわけではありません。特定の条件を満たす場合は、抵触日が発生せず、長期的な受け入れが可能になります。具体的には以下の5つの条件です。
以下で詳しく見ていきましょう。
①終了時期が明確な有期プロジェクトに従事する場合
「一定期間で完了することが明確なプロジェクト業務」に派遣される場合は、当該業務の終了時まで期間制限なく就業可能です。
たとえば、「1年間で完了するシステム導入支援」など、明確な終期が定められているプロジェクトが該当します。
※「恒常的な業務」ではなく、「明確に完了する業務」であることの証明が必要です。
②産前産後休業・育児休業・介護休業の代替要員として派遣される場合
育休や産休、介護休業などで一時的に不在となる社員の代替業務を目的とした派遣は、期間制限の適用対象外であり、該当社員が復帰するまでの間に限り、3年を超えて派遣社員を継続して受け入れることが可能です。
※契約書には「代替要員である旨」および「対象社員名・休業期間」などの明示が必要です。
③派遣社員が60歳以上である場合
派遣社員本人が60歳以上の場合、期間制限の対象から除外されます。
少子高齢化社会における就業機会の確保を目的とした特例措置であり、年齢の確認ができれば抵触日を意識せず受け入れ可能です。
④日数限定業務に従事する場合
以下2つの条件を満たす派遣社員は、期間制限の適用除外になります。
- 月の勤務日数が10日以下
- 同じ業務に従事する自社社員の所定労働日数よりも少ない
たとえば、月8日だけ勤怠システムの入力を行う派遣社員などが該当します。
ただし、シフト変更などで上限を超えた場合は対象外になるため、運用には注意が必要です。
⑤派遣社員が「無期雇用(正社員)」として派遣元に在籍している場合
派遣社員が派遣元で正社員として無期雇用契約を結んでいる場合は、派遣期間に制限はなく、抵触日は発生しません。
この形態は「常用型派遣」「正社員型派遣」とも呼ばれ、長期的な派遣活用が可能な制度として多くの企業が導入しています。
正社員型派遣についてはこちらをチェック!
ラクスパートナーズの正社員型派遣なら長期的なサポートが可能
ここまでご紹介してきたとおり、派遣社員の受け入れには「抵触日」という期限がつきものです。制度理解や期間管理には手間もリスクも伴い、「そもそもルール通りに運用できているのか不安…」というご相談も多くいただきます。
ラクスパートナーズでは、「正社員型派遣(無期雇用派遣)」を中心としたエンジニア人材サービスを提供しており、一般的な派遣の期間制限を受けず、長期的に安心してIT人材をご活用いただけます。
正社員型派遣だからこそ実現できる、長期的な人材活用
ラクスパートナーズでは、派遣するエンジニアを自社の正社員として雇用しているため、派遣期間に制限がなく、3年以上にわたり交代不要・引き継ぎ不要で同じ人材を継続的に活用できます。
特に、長期スパンのプロジェクトや属人性の高い業務を派遣に任せたいと思っている企業や、内製化を進めたい企業においては、正社員型派遣が最も安定的な選択肢です。
Web・クラウド・QA・機械学習など、専門職エンジニアをご提案
当社では、Web、インフラ・クラウドエンジニア、QAエンジニア、機械学習エンジニアなど、専門性の高い人材を正社員として採用・育成し、無期雇用型で派遣しています。
派遣先企業では即戦力として業務に参画しつつ、技術スキル・ビジネススキルの両面で安定したパフォーマンスを発揮します。


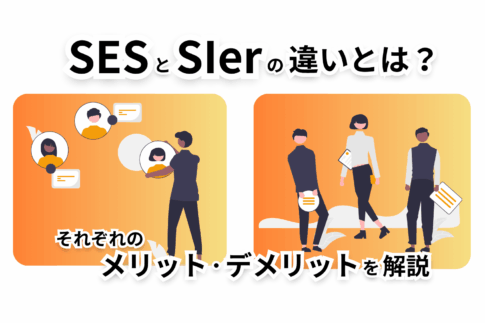


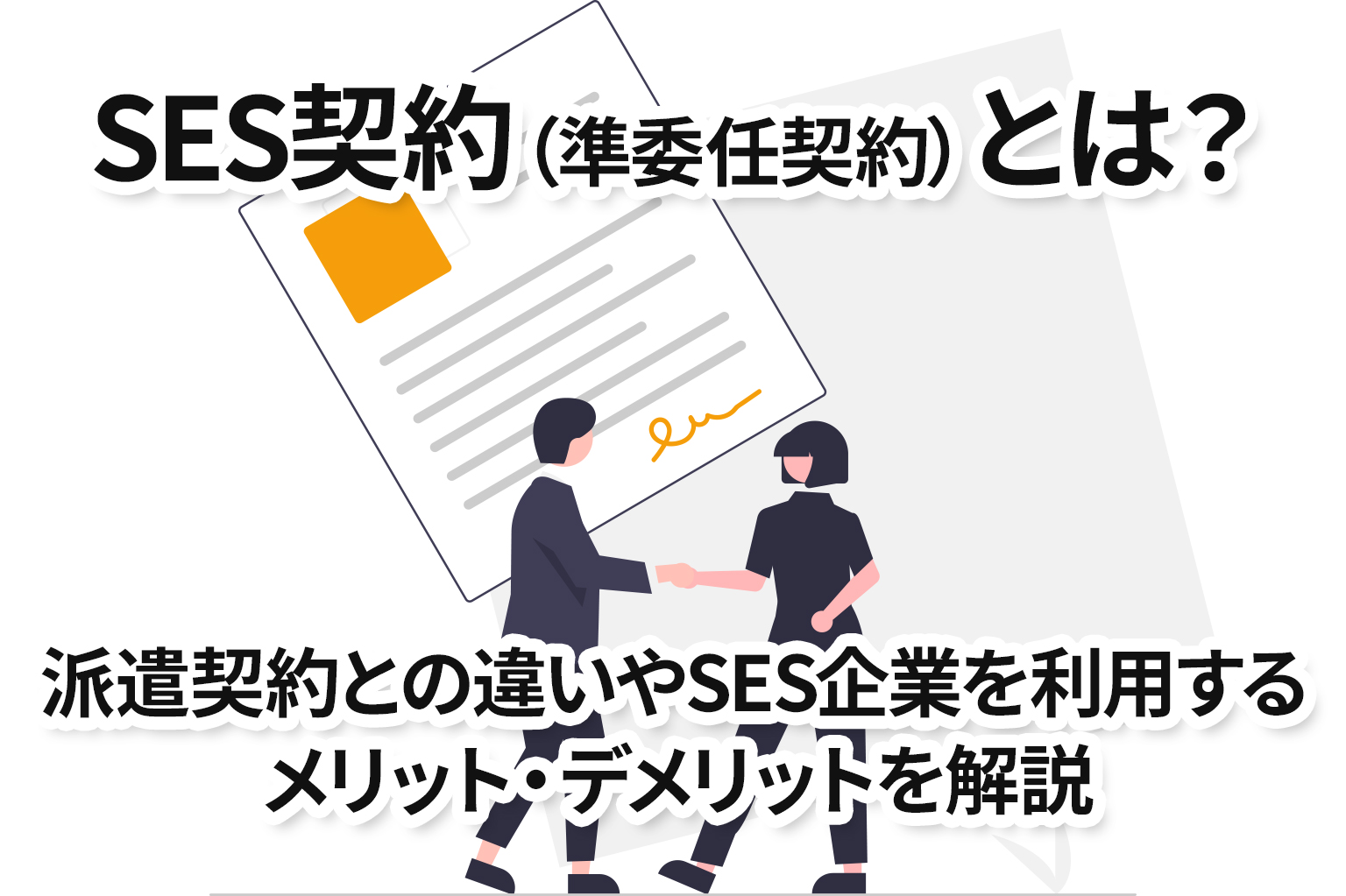


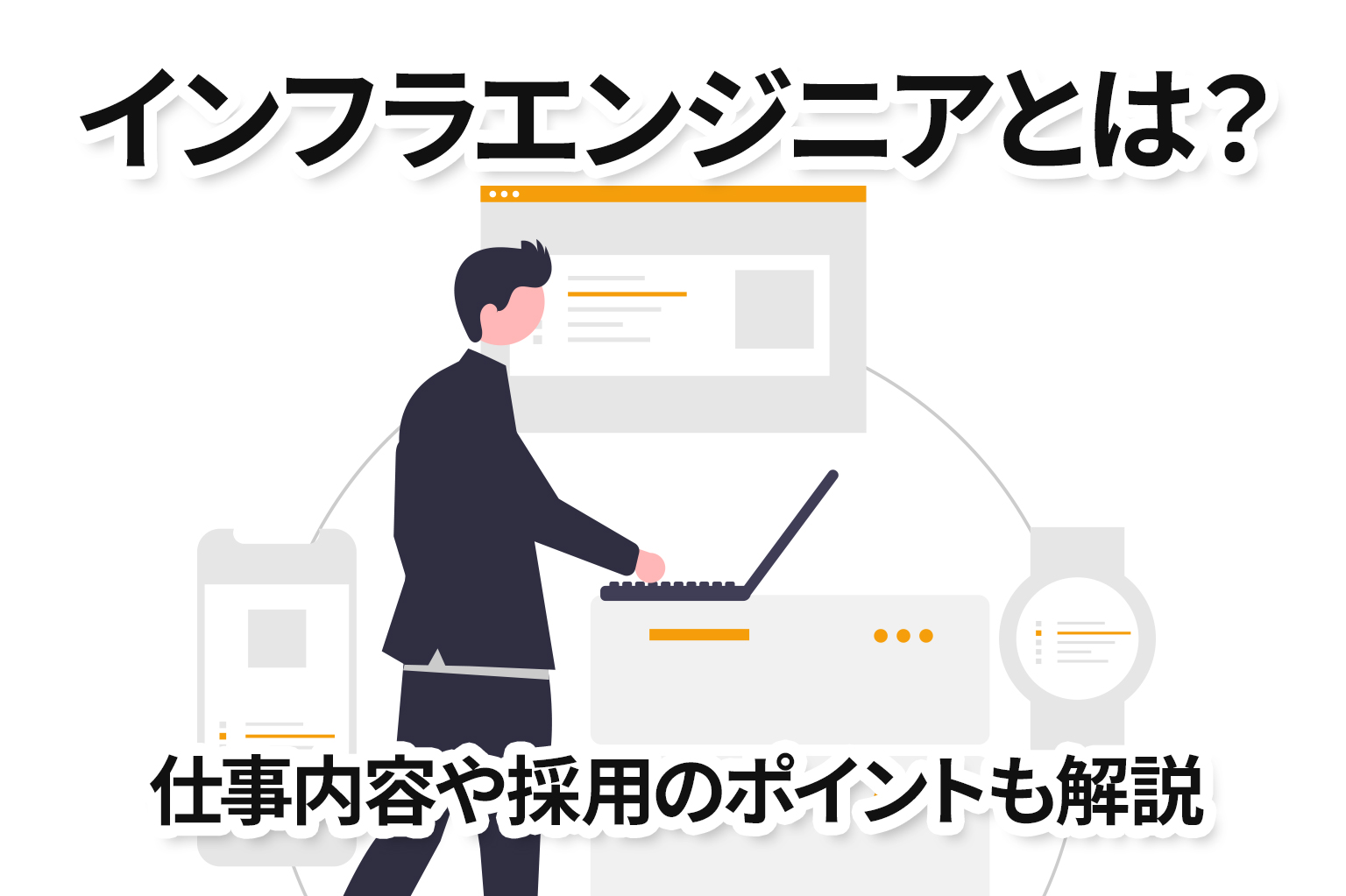
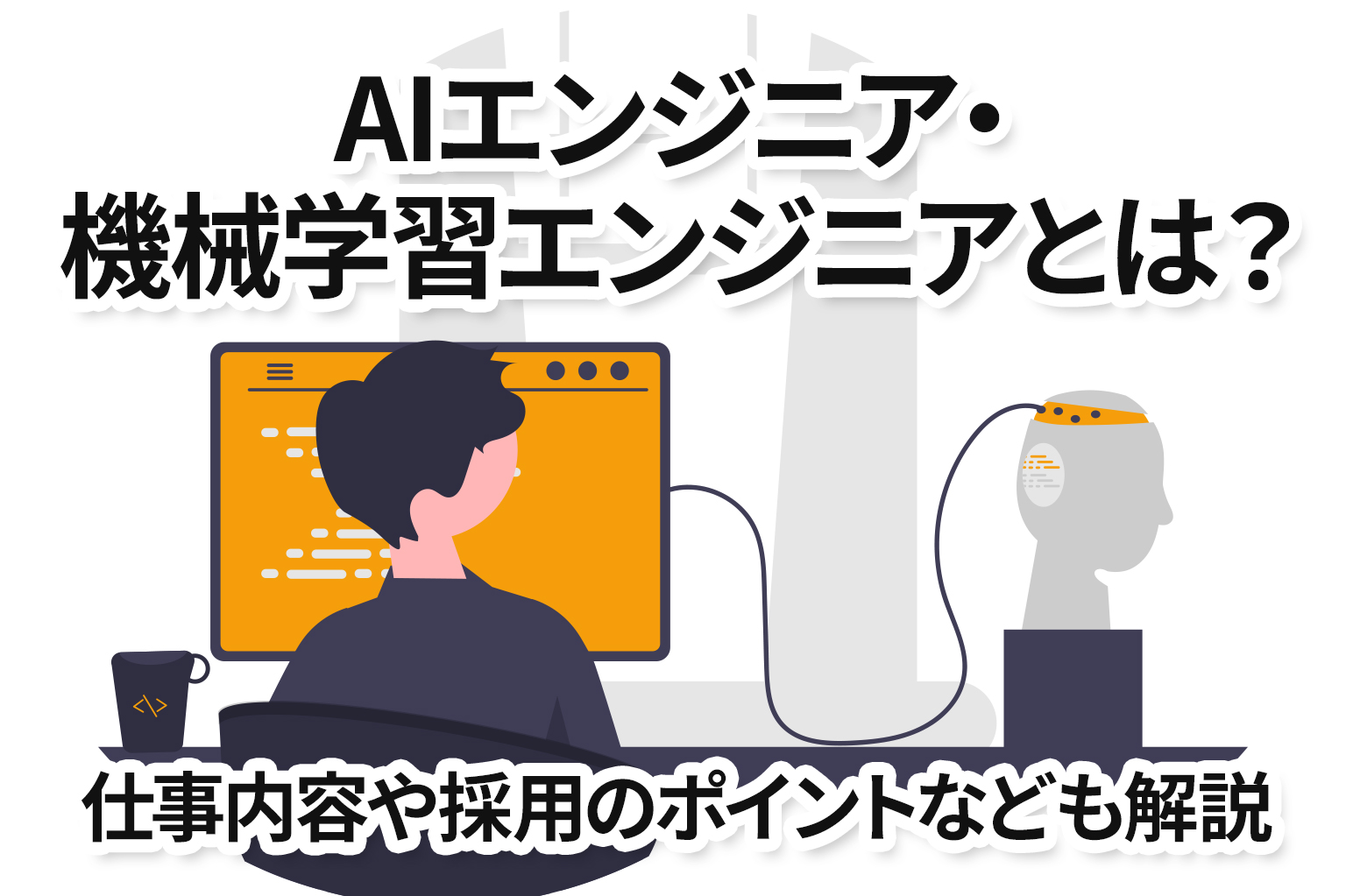

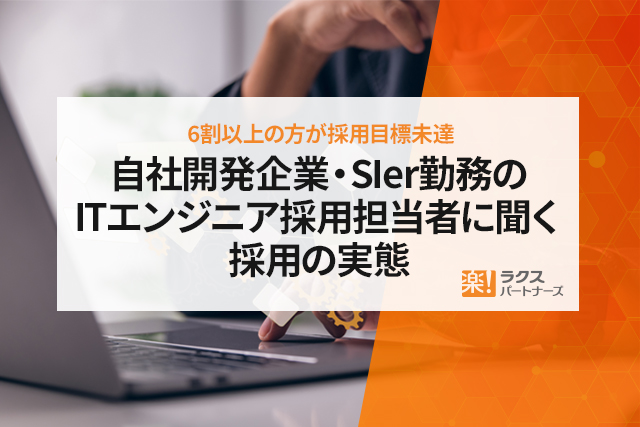
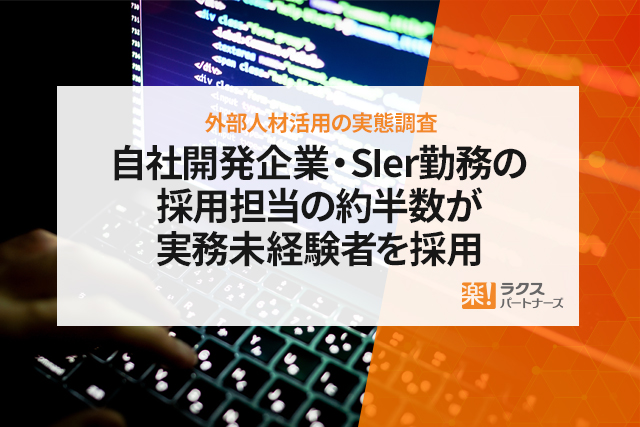
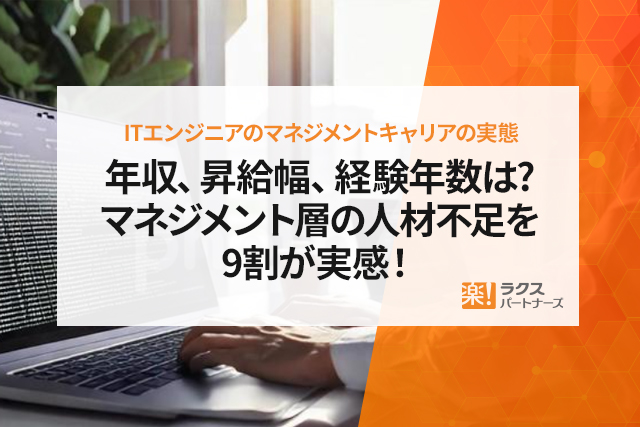
ITエンジニア採用担当者に関しての調査レポート