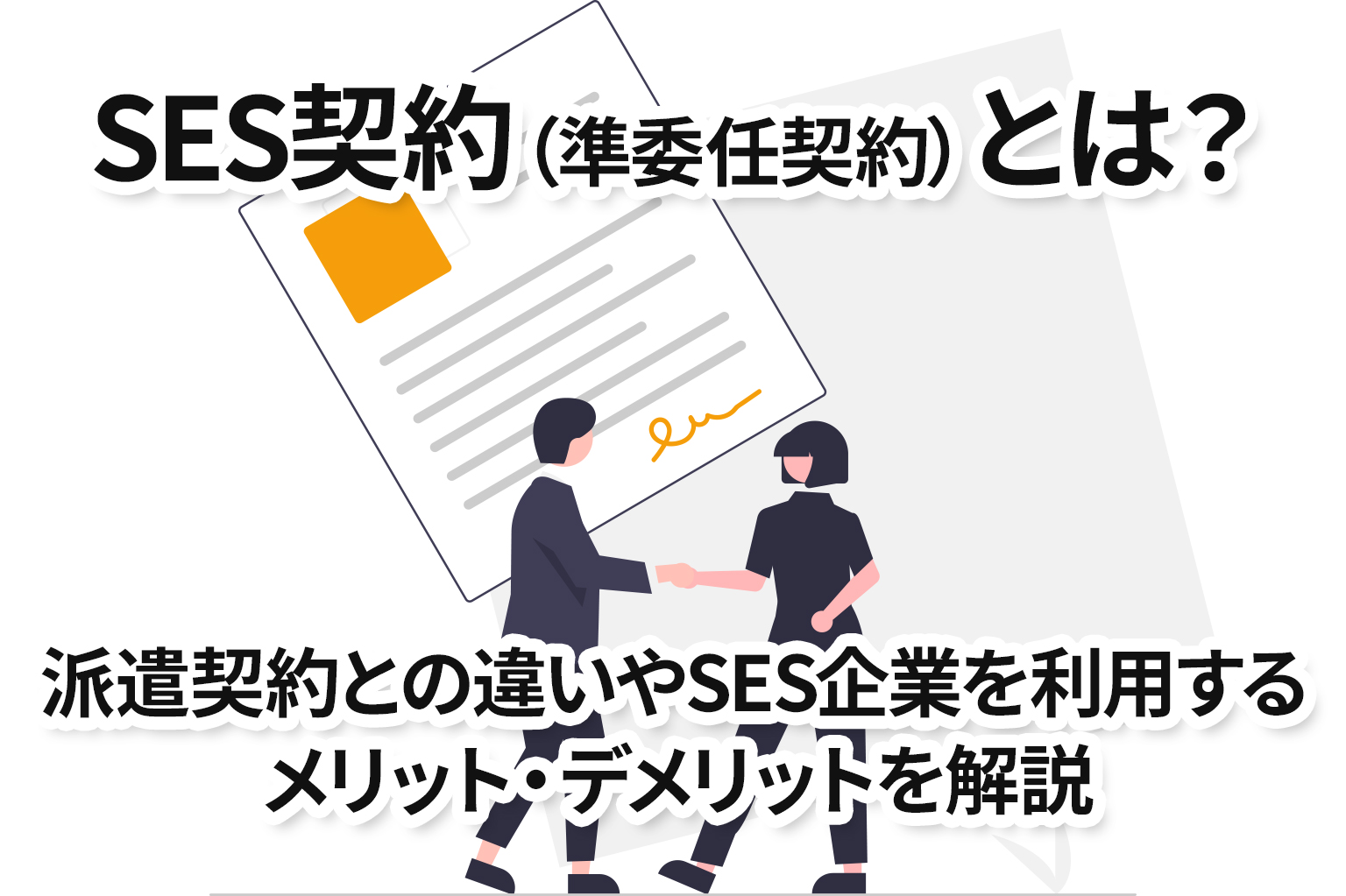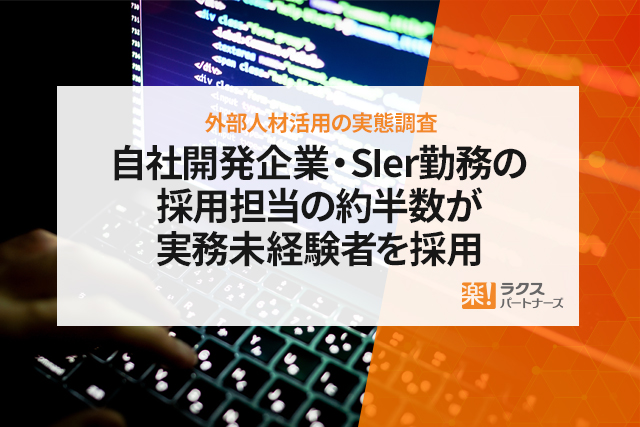DX推進やシステム内製化の加速により、企業に求められる開発体制は多様化しています。
従来の請負開発に加え、柔軟性や継続性を重視した開発手法として注目されているのが「ラボ型開発」です。
本コラムでは、ラボ型開発の概要や請負開発・オフショア開発との違い、メリット・デメリットについて解説します。
【目次】
ラボ型開発とは
ラボ型開発とは、一定期間・一定人数のエンジニアチームを専属で確保し、継続的に開発を進める開発手法です。
契約形態としてはラボ契約(準委任契約)を採用し、成果物単位ではなく、エンジニアの稼働時間や体制そのものに対して対価を支払います。
オフショア開発・ニアショア開発との違い
ラボ型開発は、もともと海外に専属の開発拠点を設ける「ODC(Offshore Development Center)」という形で普及した背景から、オフショア開発の一種として紹介されることが多くあります。
ここでよく誤解されやすいのですが、ラボ型開発を提供する企業が必ずしも海外に開発拠点を置いているとは限りません。
「ラボ型開発」は開発拠点の場所を指す言葉ではなく、契約形態とチーム体制を表す概念であるため、実際には国内の地方に開発拠点を置くケースもあり、これらは一般的に「ニアショア開発」と呼ばれています。
また近年では、首都圏を中心とした国内拠点でラボ型開発を提供する企業も増えており、このような形態は「国内ラボ型開発」と表現されることもあります。
つまり、オフショア開発かニアショア開発かといった違いは開発拠点の場所によるものであり、ラボ型開発であるかどうかは、ラボ契約(準委任契約)による専属チーム体制を採用しているかどうかで決まります。
「オフショア開発」についてはこちらをチェック!
請負開発との違い
請負開発は、あらかじめ定めた要件・仕様に基づき、成果物の完成を目的として開発を進める契約形態(請負契約)です。契約時点で開発範囲や納期、成果物を明確に定義する必要があり、発注側は完成物に対して対価を支払います。
成果物が明確なため、短期間で完結する案件や要件がしっかり固まっているプロジェクトには適しており、予算の見通しがしやすい点も特徴です。
一方、開発途中での要件変更や仕様追加は、追加契約やスケジュール調整が必要となるケースが多く、追加コストが重なる等、柔軟性とコスト面には注意が必要です。
一方で、ラボ型開発は、成果物ではなくエンジニアの稼働を前提とするため、開発を進めながら優先順位の見直しや仕様変更を行うことが可能です。継続的な改善や中長期視点でのプロダクト開発を行いたい場合、請負開発よりも高い親和性を持つ手法と言えます。
SESとの違い
SES(システムエンジニアリングサービス)は、エンジニアを一定期間派遣し、発注企業の指揮命令下で業務を行う契約形態です。エンジニアは発注企業の一員として開発に携わり、業務指示や進行管理は基本的に発注側が担います。
SESもラボ型開発も、準委任契約である点は共通していますが、最大の違いは体制と責任範囲にあります。
SESは、基本的には個人単位での参画が中心であるのに対し、ラボ型開発ではチーム単位で体制が組まれ、ベンダー側がPMやブリッジSEを置き、一定のマネジメントや品質担保を担うケースが多いです。
そのため、SESは内製リソースの一時的な補完に向いている一方、ラボ型開発は継続的な開発体制を外部と協働で構築したい場合に適しています。
「SES」についてはこちらをチェック!
請負・ラボ型開発・SESの比較
| ラボ型開発 | 請負開発 | SES | |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | ラボ契約(準委任契約) | 請負契約 | 準委任契約 |
| 体制 | チーム単位 | ベンダー主導 (成果物単位) | 基本は個人単位 (チーム編成の場合もあり) |
| 柔軟性 | 高 | 低 | 中 |
| マネジメント責任 | PM・ブリッジSE等、 ベンダー側が担うことが多い | ベンダー側 | 基本は発注側 (案件により異なる) |
| 向いている案件 | 中長期・改善型 | 要件確定・短期 | リソース補完 |
ラボ型開発のメリット
ラボ型開発は柔軟性の高い開発手法である一方、クライアントの開発フェーズや体制によっては向き不向きも存在します。以下では代表的なメリットと注意点を整理します。
メリット① 高い柔軟性
ラボ型開発では、あらかじめエンジニアの稼働工数を確保するため、開発途中での要件変更や優先順位の見直しにも柔軟に対応できます。
仕様を固めきれないフェーズや、事業環境の変化が激しいプロジェクトにおいて有効です。
メリット② 開発ノウハウを蓄積しやすい
同じ専属チームが継続的に開発を担当することで、業務知識やシステム理解が深まり、仕様の背景や改善ポイントといったノウハウが蓄積されやすくなります。
外部エンジニアと協働しながら開発を進めることで、将来的な内製化や開発力強化を見据えた体制構築がしやすい点も特徴です。
メリット③ 見積もり・契約調整の手間を抑えやすい
ラボ型開発は人月ベースの契約となるため、機能追加や仕様変更のたびに見積もりや契約調整を行う必要がありません。
その結果、クライアント側の調整工数を削減しつつ、スピーディに開発を回すことが可能となり、担当者は企画や意思決定などのコア業務に専念しやすくなります。
メリット④ アジャイル開発・継続的な開発が可能
専属チームが継続して関与することで、スプリントを回しながら改善を重ねるアジャイル開発と相性が良い点も特徴です。
単発開発ではなく、プロダクトを育てていく中長期視点の開発に適しています。
ラボ型開発の注意点
注意点① 成果物保証型ではない点への理解が必要
ラボ型開発(ラボ契約)は、エンジニアの稼働を前提とした契約形態であり、開発の自由度が高い点が特徴です。
一方で、成果物の完成をゴールとする請負開発とは異なるため、完全に成果物ベースで外注したい場合には、体制や役割分担の整理が必要になります。
注意点② 要件が完全に固まっている場合はコスト効率が合わないことも
開発内容やスケジュールが明確に定まっており、短期間で完結する案件では、請負開発の方がコストを抑えられるケースもあります。
ラボ型開発は、要件変更や継続的な改善が前提となるプロジェクトでこそ効果を発揮する手法です。
ラボ型開発が適しているケース例
ラボ型開発は、開発内容やフェーズによっては高い効果を発揮します。特に、以下のようなケースではラボ型開発との親和性が高いと言えます。
ケース① 要件が固まりきっていない、または変更が前提となるプロジェクト
事業検証やサービス改善を進めながら開発を行う場合、途中で要件や優先順位が変わることは珍しくありません。
ラボ型開発であれば、都度契約を見直すことなく柔軟に開発内容を調整できます。
ケース② 中長期的にプロダクトを育てていきたいケース
単発の開発ではなく、継続的な機能追加や改善を前提としたプロジェクトでは、専属チームによる安定した開発体制が有効です。
プロダクト理解が深まることで、開発効率や品質の向上も期待できます。
ケース③ 内製化や開発力強化を見据えている企業
外部パートナーと協働しながら開発を進めることで、業務知識や技術ノウハウを段階的に蓄積できます。
将来的な内製化や、開発体制の高度化を検討している企業にとっても適した選択肢です。
ケース④ 運用保守と小規模開発が継続的に発生する業務
日常的な運用対応や軽微な改修が多い場合、都度の見積もりや人員調整は大きな負担になります。
ラボ型開発で一定工数を確保することで、スピーディかつ安定した対応が可能になります。
ラボ型開発ならラクスパートナーズ
ここでは、ラクスパートナーズのラボ型開発による事例を一部抜粋してご紹介します。
大手SIerグループ子会社
「グループ企業向けWebサイトの運用保守・新規開発支援(ラボ型開発)」
同社では、グループ企業向けに20サイト以上のWebサイトを運用しており、日常的な更新対応や保守業務に加え、突発的な改修・小規模開発の依頼が頻発していた。
その都度、派遣や個別アサインで対応していたため、リソース確保や調整に管理コストがかかり、生産性の低下が課題となっていた。
まとめ
ラボ型開発は、要件変更への柔軟な対応や、継続的な改善を前提としたプロダクト開発に適した開発手法です。
成果物単位で進める請負開発とは異なり、エンジニアの稼働を軸とした契約形態であるため、中長期視点で開発体制を構築したい企業と高い親和性を持ちます。
一方で、すべての開発案件に最適というわけではなく、要件が明確に固まっている短期案件などでは、請負開発の方が適しているケースもあります。
自社の開発フェーズや目的、求める柔軟性の度合いを整理したうえで、開発手法を選択することが重要です。
ラボ型開発・オフショア開発・請負開発それぞれの特性を正しく理解し、自社にとって最適な開発体制を検討していきましょう。