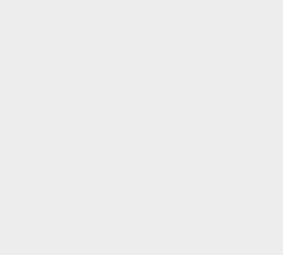営業職からエンジニアへ。未経験で飛び込んだ世界で、バックエンドからインフラ、そしてフロントエンドまで幅を広げてきたkazuakiさん。お客様からは「kazuakiさんのようなエンジニアが欲しい」と名指しで評価されるほどの信頼を築いています。
今回は、そんなkazuakiさんに、フルスタックエンジニアとして挑戦を続ける想いと、成長し続けるための考え方について語っていただきました。
当社でのキャリアの歩み方について参考にしていただけるインタビューとなっています。ぜひご覧ください。
アプリエンジニア kazuaki
2022年1月入社。
マーケティングサービスの営業職として3年間勤務したのち、エンジニアへ転身。未経験からバックエンドエンジニアとしてキャリアをスタートし、その後フロントエンドからインフラまで領域を広げながら、フルスタックエンジニアへと成長。現在は、後輩育成にも携わり、開発チーム全体の成長を支えている。
<目次>
営業職からエンジニアへ──「作る側」への憧れが転機に
――前職ではどのようなお仕事をされていたのですか?
新卒から約3年間、営業職として働いていました。
担当していたのは、ミステリーショッパー(覆面調査員)の派遣や、その調査結果を分析・可視化する自社開発ツールの販売。さらに、そのデータをもとに飲食店やサービス業の経営者の方に向けて、顧客満足度を向上するにはどうすれば良いのか、といったコンサルティング的なこともしていました。
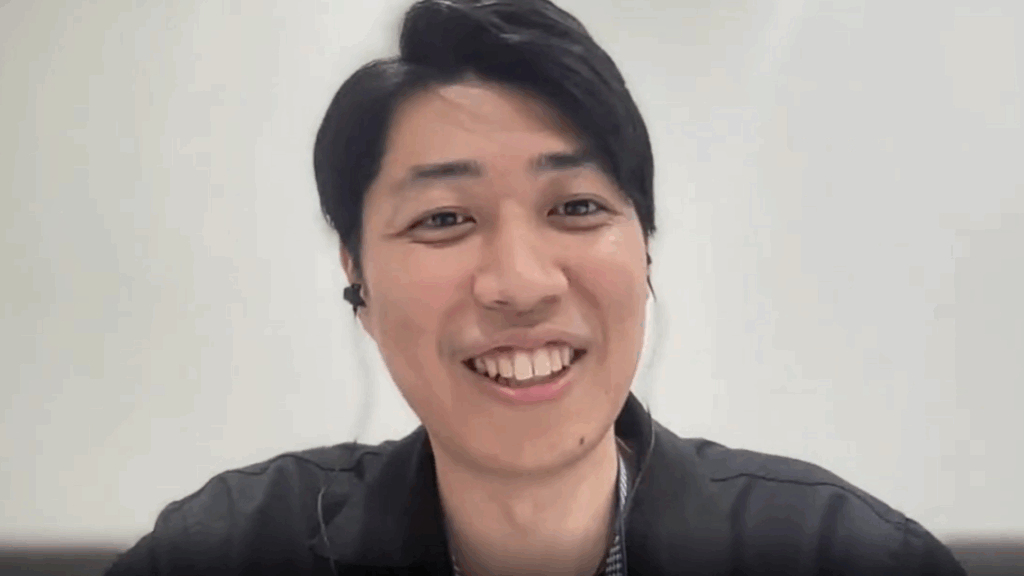
――伺っていてやりがいのある仕事内容に感じたのですが、エンジニアを目指すようになったきっかけは何だったのでしょうか?
理由は大きく二つあります。
ひとつは、営業という仕事があまり好きではないのかもしれない、と気づいたことです。
「KPIを達成するためにお願いする」といった場面が営業職だとどうしても多くなりがちかなと思うのですが、それが自分としてはストレスに感じてしまって、「本当にこの仕事を楽しめているのだろうか」と考えるようになったんです。
もうひとつは、「サービスを作る側」に回りたいと思ったことです。
── たしかに、目の前で「作る人たち」が活躍している姿を見ると、心が動きますよね。転職活動の時点では、もうエンジニア一択だったのですか?
はい。エンジニアになると決めて、未経験でも受け入れてくれる会社を探していました。
── 実際にエンジニアという仕事について調べたりする中で、どんな印象を持たれましたか?
「自分でも、一生懸命学べばできるのではないか?」と考えました。
前職で一緒に働いていたエンジニアの方々の姿を見ていたこともあって、抵抗みたいなものはなかったです。
もちろん、実際にやってみないと分からない部分もありましたが、エンジニアという仕事に対する印象は転職活動を通しても変わらず、当初から一貫して「きっとなんとかなる」「やってみたい」という前向きな気持ちでした。
── そして実際に、今ではしっかり活躍されているわけですね。
はい、ありがたいことに。これまでの人生を振り返ってみても、少し触って「いけそうだ」と感じたことは、大抵なんとかなってきました(笑)
その経験のせいか、私は自分のことをどちらかというと要領の良いタイプだと思っています。だからこそ、エンジニアという新しい分野にも、迷わず踏み出せたのかもしれません。
きっかけは身近なエンジニア──憧れが導いたバックエンドの道
── kazuakiさんはバックエンドを担当するエンジニアとして入社されていますが、最初からバックエンドを志望されていたのでしょうか?
そうですね。当時、仲の良かった開発部長に「エンジニアになりたい」と相談したところ、「まずはバックエンドをできるようになれば、フロントエンドやインフラなど他の分野にも応用が利きやすいよ」とアドバイスをもらい、バックエンドに決めました。
── 同じ会社の方に相談されていたんですね。関係性がしっかり作れていないとなかなか出来ないことだと思います。では、数ある会社の中でも、当社を選んだ決め手は何だったのでしょうか?
実は前職の時に、当社から来ていたエンジニアの方がいたんです。
その方は人柄やコミュニケーション力がダントツに素晴らしくて、少し憧れのような気持ちもありました。いつも丁寧に話を聞いてくださり、専門的な内容も分かりやすく説明してくれて、その姿が強く印象に残っていました。
── そのエンジニアの方との出会いが、大きなきっかけになったんですね。転職活動を進める中で、何か不安に感じたことはありましたか?
未経験で受け入れてくれる会社を探していたので、「本当にコードを書かせてもらえるのだろうか」「Excel作業ばかりだったらどうしよう」といった不安は常にありました。
だからこそ、実際に社員の方を知っている会社のほうが安心できると考えたんです。さらに、転職について相談していた開発部長と当社取締役が知り合いだったという偶然も重なって、面接を受けることになりました。
学びを楽しんだ研修期間──“よくできたカリキュラム”に感心
── ご縁がつながって無事に入社され、いよいよ研修が始まったわけですが、実際に受けてみていかがでしたか?
簡単だった…というと、少し語弊がありますね(笑)。
未経験者でも迷わず学べるように、基礎から順を追って理解を深めていける構成になっていて、進むほどに「うまく設計されたカリキュラムだな」と感じながら受けていました。
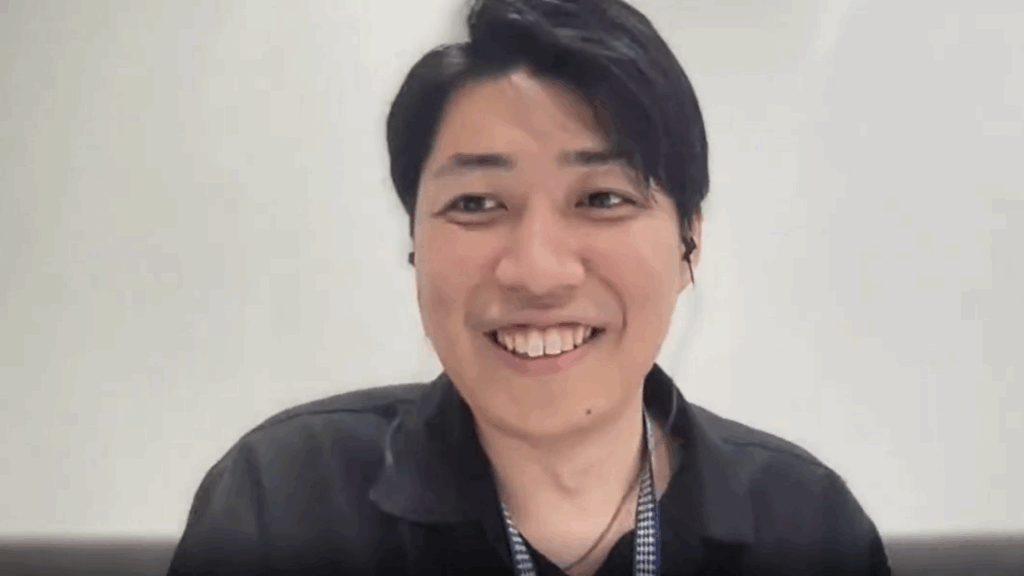
── 入社前に、ご自身でプログラミングの勉強などはされていたのでしょうか?
ProgateでJava(プログラミング言語)とSQL(データベース言語)のコースを一通り終わらせてから研修に臨みました。
それだけの予習でも研修内容がすっと頭に入ってきたので、内容の良さを実感しましたね。
怒涛のステップアップ──参画後、わずか4ヶ月でフルスタック開発
── kazuakiさんは2022年1月に入社され、同年6月から現在の現場に参画されていますね。4年近く同じ環境で活躍されているのは珍しいと思います。アサインされるまでの期間は、どんなお気持ちでしたか?
不安で仕方なかったです。
研修は終えたものの、実務でどういう知識が求められるのか全く想像がつかず、何をアピールすればいいのかも分からない状態でした。その間は、とにかく研修で扱ったJavaの知識を深めることに集中していましたね。
── 金融系の現場ですが、紹介された当初はどんな印象を持たれましたか?
ご紹介いただいて嬉しいという気持ちはありつつ、「金融系か…」と、少し構えてしまう気持ちはありました。
勝手に金融系の企業は、レガシーな技術や厳しい働き方だと想像してしまっていたんです。とはいえ、まずはどこかの現場で経験を積まなければ何も始まらないので、「頑張るか」という気持ちでもいました。
── 実際に参画されて、最初に任されたタスクは何だったのですか?
React(JavaScriptライブラリ)を使ったフロントエンドのタスクでした。
── えっ、研修はJavaだったはずですよね?
はい(笑)。もちろん参画時点でクライアント向けサービスの開発に関わることは聞いていて、その技術スタックの中にReactがあったんですよ。それを知っていたので、参画が決まってから業務開始までの期間に、独学でReactを予習しました。
実務は未経験なので、何でもやってみるしかないと思いましたし、むしろ「いろいろな技術に触れられるのは、成長のチャンスだ」と捉えました。結果的に、なんとかなりましたね(笑)

── 開発部長がおっしゃっていた「まずはバックエンドをできるようになれば、フロントエンドなど他の分野にも応用が利くよ」というのが、早くも現実になったわけですね(笑)Javaを学んでいたことが役立った部分もありましたか?
ありました。もちろん違いは多いですが、Javaに限らず、一つの言語を基礎からしっかり学んでおけば、他の言語にも応用できるというのが、今の私の考えです。基本的なルールはどの言語も大体同じですから。
未経験スタートだからこそ、知識がない分研修中に「他の言語が気になる」こともあると思います。自分もそうでした。
でも、まずは「一つの言語をしっかりやりきる」ことが大切だと思います。基礎を固めた経験は、後になって確実に自分を支えてくれると、実体験から強く感じています。
── 何事も基礎が大事ですね。具体的な業務内容としては、どんなものだったんでしょうか?
最初は、証券アプリのバグ修正や、表示・非表示の切り替えなど、比較的シンプルなタスクから始まりました。
ただ、そこからの展開がかなり早くて、参画して4ヶ月後には新しいサービスのページを1から作ることになったんです。
PV数が5万ほどあるページで、既存アプリの1階層下にあたる部分でした。
── それは急展開ですね!責任重大ですが、率直にどう思いましたか?
「マジか」と思いましたが、同時に「なんとかなるだろう」とも思いました(笑)
サービスは部署内で完結していたので他部署との調整などはなく、同じ部の方々に仕様の確認やレビューをお願いしながら進められました。おかげで技術面への不安はそこまで大きくありませんでした。
ただ、フロントエンド、API(バックエンド)、バッチ処理までをすべて一人で担当することになったため、「納期に間に合うかどうか」が唯一の心配ごとでしたね。
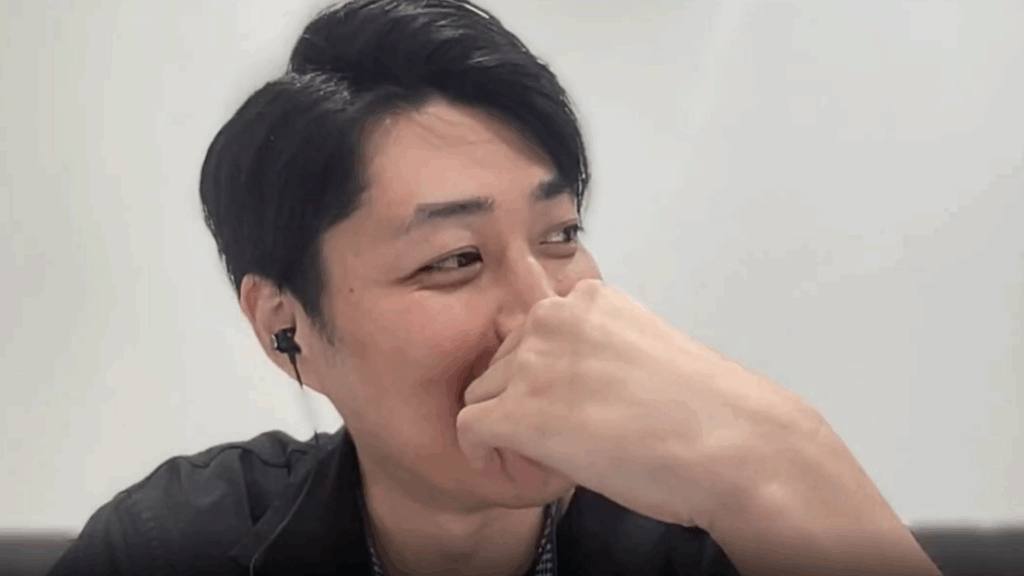
── 4か月でそこまで任されるのは、本当にすごいですね。
おそらく、最初の修正タスクを早く正確にこなしていたことで、「任せても大丈夫そう」と思っていただけたのだと思います。当時の自分のコードを見ると「なんでこんな書き方したんだろう」と思うことも多々ありますが(笑)、それもまた成長の証だと感じています。
挑戦への貪欲──バックエンド、フロントエンド、インフラ、そしてフルスタックへ
── その後はどのような業務を担当されたのですか?
引き続きアプリケーション開発を行いながら、Webサービスのサーバーをオンプレミス環境(自社保有)からAWS(クラウド)へ移管するプロジェクトに携わることになりました。
── インフラエンジニアの領域まで学ばれたということですか?
そうなんですよ(笑)。ただ、当時は開発タスクをいただいても、いただく度に早めに終わらせてしまっていて、手が空きやすくなっていたんです。上長に「今ちょっとタスクに余裕があるんですよね」とアピールしていたら、「じゃあAWSやってみる?」と言われて、「やります!」と即答しました(笑)
── どうやってキャッチアップされたんですか?
社内のインフラ担当の方に教えてもらいながら、実践で学びました。
「この設定で合っていますか?」「社内ルール的には大丈夫ですか?」と確認を重ねながら、試行錯誤で進めていった感じです。
── お話を聞いていると、自社の正社員でもなかなか難しいのでは?と感じるような動きをされている印象を受けます。kazuakiさんがそれだけ挑戦し続けられる原動力はどこにあるのでしょう?
やっているうちに、フルスタックとしてもっと幅広くスキルを身につけたいという気持ちが強くなってきたからかもしれません。だから、日ごろからAWSも隙あらば学びたいと思っていたんですよ。

あとは単純に、同じことをやっていると飽きてしまう個人的な性格の問題ですかね(笑)。
開発業務も慣れてくるとだんだん頭を使わなくなってしまいます。新しいことに挑戦する方が刺激があって楽しいですし、自分の知識も増えます。 だから、「やったことないこと、知らないことだからやらない」とは思わず、むしろ自分を飽きさせないために、積極的に新しいことに突っ込んでいくタイプです。
フルスタック化した後、現在の業務──Flutterでネイティブアプリ化
── 現在はどんな業務を担当されているのですか?
これまで携わってきたWebサービスのネイティブアプリ化(スマートフォンなどの端末にインストールするアプリにすること)を行っています。
Web版は言語がTypeScript、フレームワークはNext.jsで作られていましたが、ネイティブアプリのフレームワークはFlutterを使っており、言語はDartです。
── また新しい言語が出て来ましたね。Webとネイティブアプリでは開発の考え方が違う印象もありますが、スムーズに対応できるものなのでしょうか?
意外といけますよ。やはり、どの言語もベースとなる考え方や基本的なルールは大体同じなんです。
これまでの業務でFlutter以外にも、AWSではPython、既存バッチではRubyを扱いましたが、根本は共通していると感じています。
違いがあるとすれば、言語ごとに推奨されるフォルダ構成やデザインパターン(設計の考え方)が違うくらいでしょうか。
そこを意識せずに書いてしまうと、動いてもメンテナンスしづらいコードになってしまうので…。それだけはキャッチアップが必要ですね。
信頼される理由──「聞くこと」と「悩むこと」の使い分け
── 営業担当の方から、「お客様から『kazuakiさんのような人が欲しい』と言われている」と伺いました。何か信頼関係を作るうえで意識していることはありますか?
あくまでも自分の場合の話ですが、とにかく一人で悩み込まないことですね。「聞いた方が早い」と思うことは、ためらわずに聞くようにしています。
── とはいえ、エンジニアは「聞く前にまず自分で調べること重要」とも聞きます。そのバランスはどう考えていますか?
そうですね、「仕様に関すること」は、すぐに聞くべきだと思っています。
特にアジャイル開発では、作りながら議論して形にしていくので、違和感を放置すると後で大きなズレになります。だから、「これって本当に使いやすいのだろうか」などと思った時点ですぐに、共有したり、質問したりしてます。
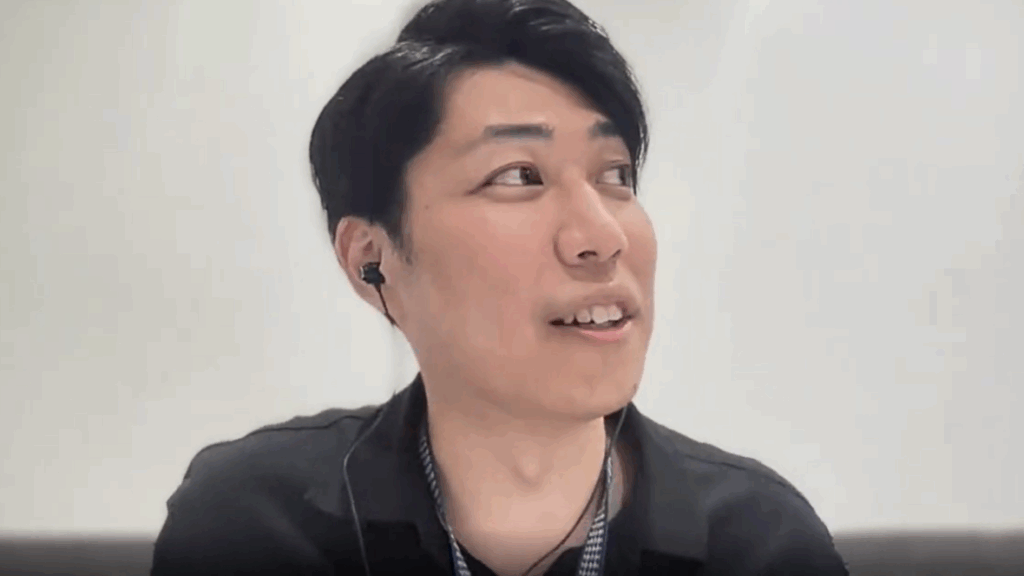
一方で、コードの書き方については、一度自分でしっかり悩むべきだと考えています。試行錯誤するプロセスが、自分の力になることを今までの経験上でも感じています。それでも分からなければ聞きますが、コードについては、基本的には自分で解決策を見つけるようにしています。
── なるほど。そういった切り分けがしっかりできているんですね。そういった姿勢が、信頼につながっているのかもしれませんね。今はフル出社とのことですが、やはりコミュニケーションは取りやすいですか?
出社は正直しんどいところもありますが(笑)、やはりレスポンスの速さがリモートとは全然違いますね。
ちょっとした確認をすぐにできるので、仕事の進み方もスムーズになっています。雑談や世間話も気軽にできるので、そういった点も、「信頼関係」にとってはプラスに働いていると思います。
後輩育成とこれから──PMとしてチームを動かす側へ
── 新しく入ってきたメンバーの育成にも関わっていると伺いました。後輩を指導する上で、意識していることはありますか?
これは、先ほどの話にも繋がるのですが、質問された時に、すぐに答えを教えないことです。
特にコードに関することは、答えを伝えるとその瞬間に思考が止まってしまいます。だから、「こういう方向から調べてみたら?」などヒントを出しつつ、自分で考えて解決してもらうように心がけています。ただ、その「言いすぎ・言わなすぎ」のバランスが難しくて、最近の悩みでもありますね。
── たしかに、その加減は難しそうですが、後輩の学びにとっては良い影響を与えていそうですね。今後のキャリアについては、どのように考えていますか?マネジメントのキャリアも関心があるのでしょうか?
そうですね、どちらかというと、PM(プロジェクトマネジメント)寄りの方向に進みたいと思っています。
最近は、コードを書くことそのものよりも、人を育てたり、チーム全体を動かしたりすることに面白さを感じ始めています。
また、これまで仕様決定の会議などにも参加させてもらう中で、技術的なバックグラウンドがあることが、議論を整理したり現実的な判断をしたりする上で大きな強みになると感じました。
だからこそ、これからは仕様を作る側としてプロジェクトを動かしながら、人を育てることにも力を入れていきたいと考えています。
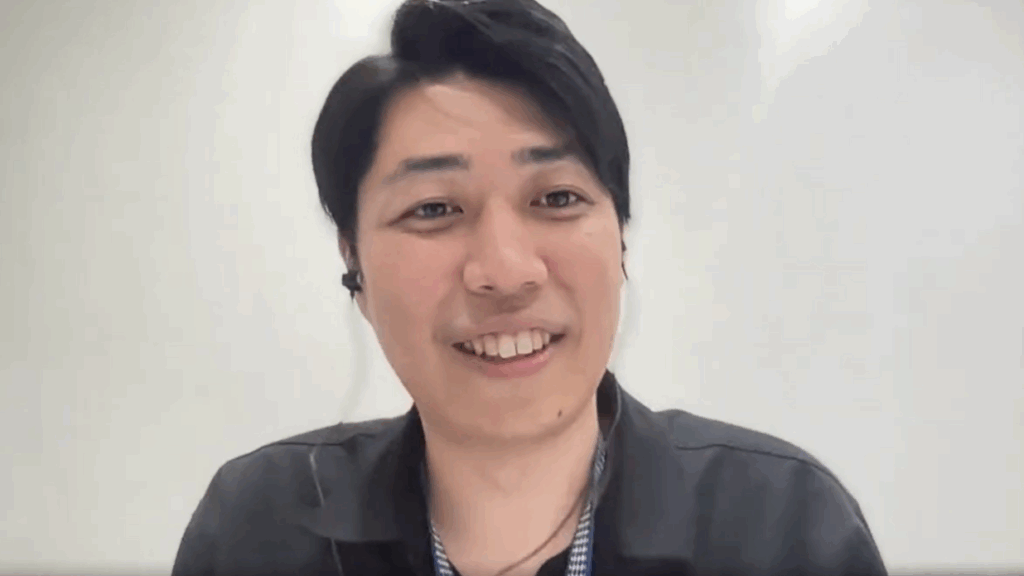
エンジニアを目指す方へ──まずは一つの言語を大切に
── それでは最後に、これからエンジニアを目指す方へメッセージをお願いします。
一番伝えたいのは、「最初に触れた言語を、まずは大切にしてほしい」ということです。
他の言語に興味が出ても、まずは一つをしっかり使いこなせるようになるまで向き合ってみてください。一つの言語を深く理解すれば、次に学ぶときの吸収力がまるで違いますし、どんな技術にも応用が利くようになります。それが、エンジニアとしての成長を支える基盤になると思います。
── ありがとうございます。エンジニアになってみて、改めてどうですか?
楽しいですよ。
営業時代に抱えていたストレスが全くなくなり、自分はこの仕事に本当に興味があるんだな、と実感しています。新しいスキルを身につけるたびに、自分の世界が少し広がる。それがやりがいに繋がりますし、エンジニアという仕事の魅力だと思います。
編集後記
営業職からエンジニアへ転身し、バックエンドを起点にフロントエンドやインフラまで領域を広げてきたkazuakiさん。
人との関わりからチャンスを掴み、確かな自信と努力で着実にステップアップしてきました。
技術の習得を楽しみながら、どんな挑戦にもまっすぐに踏み出していく──前進を惜しまない姿が胸に響くインタビューでした。
エンジニアのキャリアにチャレンジしてみたい!と思っている方は、まずオンライン採用説明会から参加してみませんか?
オンラインで定期開催中ですので、ぜひチェックしてみてください!
エンジニアのキャリアにチャレンジしてみたい!と思っている方へ。
お気軽にオンライン説明会にご参加ください!